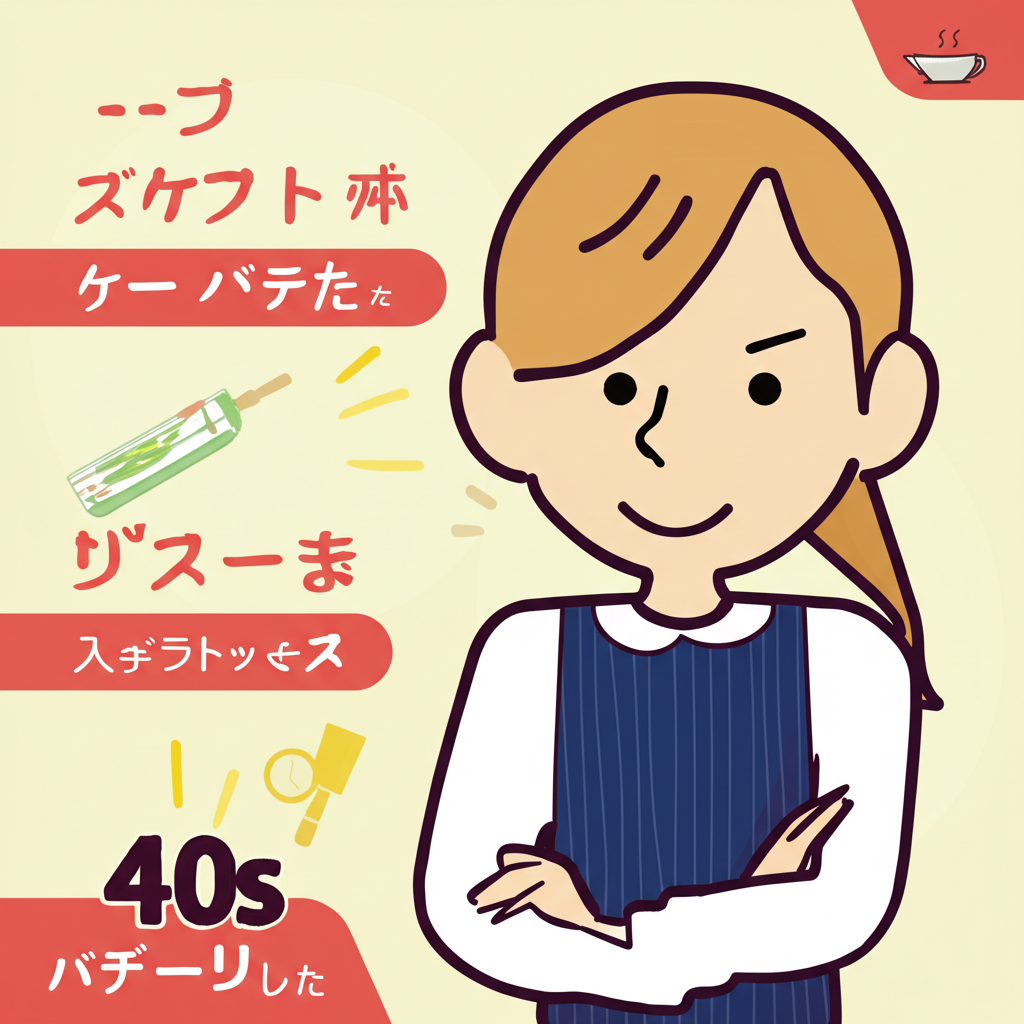40代は体や健康状態の変化を感じやすい時期であり、将来の健康のために生活習慣を見直すことが重要です。
この記事では、健康診断の結果や日々の不調に気づき、無理なく続けられる食事・運動・睡眠などの具体的な改善策と、モチベーション維持のコツを解説します。

最近疲れやすいし、健康診断の数値も気になる…何から始めればいいんだろう?

ご自身の生活を振り返り、できることから少しずつ改善していきましょう
- 40代が生活習慣を見直すべき理由とチェック方法
- 食事・運動・睡眠・ストレス・禁煙/節酒の具体的な改善策5つ
- 改善を無理なく続けるためのモチベーション維持のコツ
- 生活習慣改善に関するよくある疑問と回答
40代から意識したい、生活習慣の見直しポイント
40代は体や健康状態の変化を感じやすい時期であり、将来の健康を見据えた生活習慣の見直しが重要になります。
健康診断の結果や日々のちょっとした体調の変化は、体からの大切なサインかもしれません。
ご自身の状態を正しく把握し、放置するリスクを知ることで、改善への第一歩を踏み出すことができます。
この章では、健康診断結果と体からのサインの見方、放置するリスクと将来への影響、生活習慣が乱れる原因、そして自分自身の生活習慣をチェックする方法について詳しく見ていきましょう。
ご自身の生活を振り返り、改善点を見つけるきっかけにしてください。
健康診断結果と体からのサインの見方
健康診断の結果を受け取ったら、まず基準値とご自身の数値を比較してみましょう。
特に注目したいのは、血圧、血糖値(HbA1c)、脂質(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)、肝機能(AST、ALT、γ-GTP)、肥満度(BMI)などです。
これらの数値が基準値を超えている場合、生活習慣の見直しが必要なサインと考えられます。
例えば、特定健診・特定保健指導における高血圧の基準は収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上とされています。
数値だけでなく、「最近疲れやすい」「階段で息切れがする」「寝つきが悪い」といった日々の体調変化も、見逃さないようにしたいです。

健康診断の結果、ちょっと数値が高めって言われたけど、具体的にどう見ればいいのかな…

数値の意味を正しく理解し、体からのサインと合わせて考えることが大切ですよ
健康診断の結果や体からのサインは、将来の健康を守るための道しるべとなります。
放置するリスク、将来の健康への影響
健康診断で指摘された数値を「まだ大丈夫だろう」と放置してしまうと、将来的に深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。
特に生活習慣病と呼ばれる、糖尿病、高血圧、脂質異常症のリスクが高まります。
これらの病気は自覚症状がないまま進行することが多く、気づいた時には心筋梗塞や脳卒中といった、命に関わる重大な病気につながることも少なくありません。
厚生労働省の調査によると、日本人の死因の上位には、がん、心疾患、脳血管疾患が挙げられており、これらの多くに生活習慣が関わっていることが分かっています。

今は特に症状がないから、まだ大丈夫かなって思っちゃうんだよね…

自覚症状がないからこそ、早めの対策で将来のリスクを減らすことが重要なんです
今の生活習慣を見直すことが、10年後、20年後の健康な自分への投資となるでしょう。
生活習慣の乱れ、よくある原因の特定
生活習慣が乱れてしまう原因は人それぞれですが、40代の方によく見られる原因をいくつか挙げてみましょう。
- 仕事の忙しさ: 残業や不規則な勤務時間による食事時間の乱れや睡眠不足は、生活リズムを崩す大きな原因となります。
- 食生活の偏り: 外食やコンビニエンスストアの利用が増えると、塩分や脂質の過剰摂取、野菜不足になりがちです。特に遅い時間の食事は、肥満や睡眠の質の低下につながります。
- 運動不足: デスクワーク中心の生活や、通勤で車を使うことが多い場合、意識的に体を動かす機会が減ってしまいます。
- ストレス: 仕事や家庭でのストレスから、過食や飲酒量の増加につながるケースも見られます。

忙しいと、どうしても食事が不規則になったり、運動する時間が取れなかったりするんだよなぁ

原因を特定することで、ご自身に合った改善策を見つけやすくなりますよ
まずはご自身の生活を振り返り、どこに原因があるのかを把握することが改善の第一歩です。
自分自身の生活習慣のチェック方法
ご自身の生活習慣を客観的に把握するために、具体的な方法でチェックしてみましょう。
まずは、1週間の食事内容、運動時間、睡眠時間、飲酒量などを記録することから始めるのがおすすめです。
手書きのノートでも良いですし、「あすけん」や「눔 (Noom)」といった健康管理アプリを活用すると、カロリーや栄養バランスも可視化できて便利です。
記録を振り返ることで、「思ったより塩分を摂っているな」「体を動かす時間が少ないな」といった具体的な課題が見えてきます。
以下のチェックリストも参考に、ご自身の生活習慣を見直してみてください。
| チェック項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 1日3食、規則正しい時間に食べている | □ | □ |
| 食事の栄養バランスを意識している | □ | □ |
| 野菜を十分に摂れている | □ | □ |
| 塩分や脂質の多い食事を控えめにしている | □ | □ |
| 間食や甘い飲み物を摂りすぎていない | □ | □ |
| 週に2日以上、30分程度の運動をしている | □ | □ |
| 日常生活で階段を使うなど、体を動かす工夫をしている | □ | □ |
| 毎日6~8時間程度の睡眠をとれている | □ | □ |
| 寝る前にリラックスする時間がある | □ | □ |
| ストレスを上手に解消できている | □ | □ |
| 喫煙習慣がない | □ | □ |
| 飲酒は適量(または飲まない) | □ | □ |

こうして見ると、できていない項目が結構あるかも…

まずは課題を把握することが大切です。一つずつ改善していきましょう
現状を正確に知ることで、具体的な改善目標を設定しやすくなります。
無理なく続けるための生活習慣改善、5つの具体策
生活習慣の改善において最も重要なのは、無理なく継続することです。
一度に完璧を目指すのではなく、できることから少しずつ取り入れて、習慣化していくことが成功の鍵となります。
ここでは、食事、運動、睡眠、ストレス、そして禁煙・節酒という5つの具体的な改善策をご紹介します。
これらのポイントを意識することで、健康的な生活への第一歩を踏み出せます。
食事改善、塩分や時間の工夫から
毎日の食事は、私たちの体を作る基本です。
塩分の摂りすぎは高血圧のリスクを高め、食べる時間が不規則だと体に負担がかかります。
厚生労働省が推奨する1日の塩分摂取目標量は、男性で7.5g未満、女性で6.5g未満とされています。
外食や加工食品が多いと、知らず知らずのうちに塩分を摂りすぎていることがあります。
また、夜遅い時間の食事は、肥満や睡眠の質の低下につながります。
できるだけ就寝3時間前までには夕食を済ませることを心がけましょう。
| 塩分を減らす工夫 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 調味料の使い方 | かけるより「つける」、減塩タイプを選ぶ |
| 加工食品の選び方 | 栄養成分表示を確認、ハムや練り製品は控える |
| 汁物 | 具沢山にする、1日の摂取量を減らす |
| 香辛料や香味野菜の活用 | 唐辛子、こしょう、ハーブ、生姜、にんにくなどで風味付け |
| 外食時の注意 | 定食の汁物は残す、麺類のスープは飲み干さない |

外食やコンビニが多くて、塩分が気になるけど、どう減らせばいい?

調味料の使い方や食品選びの工夫で、無理なく減塩できますよ
まずは、醤油やソースをかける習慣から、小皿にとってつける習慣に変えることから始めてみてはいかがでしょうか。
少しの工夫で、食生活は着実に改善されていきます。
運動不足解消、日常に取り入れるヒント
運動不足は、肥満や生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、体力や気力の低下にもつながります。
運動と聞くと、ジムに通ったり、ランニングをしたりといった特別なことをイメージするかもしれません。
しかし、忙しい毎日の中で日常生活に運動を取り入れることが、継続の秘訣です。
例えば、エレベーターではなく階段を使う、一駅分歩く、少し遠くのスーパーへ買い物に行くなど、意識的に体を動かす機会を増やしましょう。
目標としては、1日合計で30分程度の運動や、1日8000歩程度を目指すと良いとされています。
| 日常で運動量を増やすヒント | 具体的な方法 |
|---|---|
| 通勤・移動時 | 一駅手前で降りて歩く、自転車を利用する、階段を使う |
| 仕事中 | こまめに立ち上がる、ストレッチをする、軽い筋トレをする |
| 家事 | 掃除や洗濯をキビキビ行う、庭の手入れをする |
| 買い物 | 歩いて買い物に行く、少し遠回りをする |
| 休日 | ウォーキング、サイクリング、軽いスポーツを楽しむ |

ジム通いは続かなかったけど、運動不足は解消したい…

特別な運動ではなく、日常生活の中で「ついで」に体を動かすことから始めましょう
座りっぱなしの時間を減らし、こまめに体を動かすことを意識するだけでも効果があります。
まずはご自身ができそうなことから、気軽に取り組んでみましょう。
睡眠の質向上、寝る前の新習慣
十分な睡眠時間を確保することはもちろん大切ですが、睡眠の質を高めることも健康維持には欠かせません。
睡眠の質とは、ぐっすり眠れて、朝すっきりと目覚められるかどうかということです。
睡眠不足や質の低い睡眠は、日中の集中力低下や疲労感だけでなく、生活習慣病のリスクも高めます。
質の高い睡眠のためには、寝る前の過ごし方が重要です。
就寝前の1〜2時間は、心身をリラックスさせる時間にしましょう。
スマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトは睡眠を妨げるため、避けるのが賢明です。
| 睡眠の質を高める寝る前の習慣 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 入浴 | 就寝90分前までに、ぬるめのお湯(38~40℃)にゆっくり浸かる |
| リラックスタイム | 読書、軽いストレッチ、瞑想、ヒーリング音楽を聴く |
| 飲み物 | カフェインやアルコールを避ける、温かいノンカフェイン飲料 |
| 照明 | 就寝に近づくにつれて部屋の明かりを暗くする |
| 寝室環境 | 温度・湿度を快適に保つ、体に合った寝具を選ぶ |

寝つきが悪くて、疲れが取れない感じがする…

寝る前の過ごし方を見直すだけで、睡眠の質はぐっと上がります
毎日決まった時間に寝起きすることも、体内時計を整え、睡眠の質を高めるために有効です。
自分に合ったリラックス方法を見つけ、心地よい眠りを目指しましょう。
ストレスとの上手な付き合い方発見
現代社会において、ストレスを完全になくすことは難しいかもしれません。
しかし、ストレスと上手に付き合う方法を見つけることは、心身の健康を保つ上で非常に重要です。
過度なストレスは、暴飲暴食、睡眠不足、意欲低下などを引き起こし、生活習慣の乱れにつながります。
まずは、自分が何にストレスを感じているのかを把握し、自分なりの解消法を見つけることから始めましょう。
1日に10分でも良いので、自分の好きなことに時間を使ったり、リラックスできる時間を持ったりすることが大切です。
| 自分に合ったストレス解消法を見つけるヒント | 具体的な方法 |
|---|---|
| 気分転換になる活動 | 趣味に没頭する、音楽を聴く、散歩する、友人と話す |
| リラックスできる活動 | 入浴、アロマテラピー、瞑想、深呼吸、ヨガ、ストレッチ |
| 休息 | 十分な睡眠をとる、昼寝をする、何もしない時間を作る |
| 問題解決へのアプローチ | 問題の原因を分析する、解決策を考える、人に相談する |
| 考え方を変える | ポジティブに捉える、完璧主義を手放す、物事の受け止め方を変える |

仕事のストレスで、つい飲みすぎたり食べ過ぎたりしてしまう…

自分なりのリラックス方法を見つけて、ストレスを溜め込まない工夫が大切です
ストレスを感じたときに、つい飲食に走ってしまう場合は、代替となる行動を見つけることが有効です。
ストレス管理も、健康的な生活習慣を維持するための重要な要素と考えましょう。
禁煙と節度ある飲酒への挑戦
喫煙や過度の飲酒が、がんや生活習慣病のリスクを高めることは広く知られています。
健康のために禁煙や節度ある飲酒を心掛けることは非常に重要です。
節度ある飲酒とは、厚生労働省によると、1日あたりの純アルコール量で約20g程度とされています。
ビール中瓶1本、日本酒1合、ワイングラス2杯弱が目安となります。
女性や高齢者はこれよりも少ない量が推奨されます。
禁煙や節酒は、強い意志が必要な場合もありますが、具体的な目標設定と計画的なステップを踏むことで成功しやすくなります。
| 禁煙・節酒を成功させるためのステップ | 具体的な方法 |
|---|---|
| 目標設定 | 禁煙開始日を決める、週に2日休肝日を設ける、1日の飲酒量を決める |
| 環境整備 | たばこや灰皿を処分する、飲み会の誘いを断る、ノンアルコール飲料を用意する |
| 代替行動 | ガムを噛む、軽い運動をする、趣味に没頭する、炭酸水を飲む |
| 周囲の協力 | 家族や友人に宣言する、禁煙仲間や節酒仲間を作る |
| 専門家のサポート | 禁煙外来を受診する、保健所や専門機関に相談する |

お酒を減らしたいけど、付き合いもあるし、なかなか難しい…

いきなりゼロを目指さず、目標を決めて少しずつ減らしていくのが成功のコツです
禁煙や節酒は、ご自身の健康を守るための大切な投資です。
必要であれば専門家のサポートも活用しながら、無理なく取り組んでいきましょう。
周囲の理解と協力を得ることも、成功への大きな助けとなります。
「続けられない」を防ぐ、モチベーション維持と工夫
生活習慣の改善において、多くの方が直面する壁が「継続」です。
良いとわかっていても、日々の忙しさや誘惑の中で続けることは簡単ではありません。
ここで最も重要になるのが、モチベーションの維持です。
継続のためには、小さな目標を設定して達成感を得ること、行動や効果を記録して可視化すること、家族など周囲の協力を得ること、完璧を目指さない考え方を持つこと、そして便利なアプリなどを活用することが有効です。
これらの工夫を取り入れることで、改善への意欲を保ちやすくなります。
無理なく、そして楽しみながら生活習慣を変えていくための具体的なヒントを、これからご紹介します。
小さな目標設定と達成感の重要性
生活習慣改善を始めようとするとき、つい大きな目標を立ててしまいがちですが、それが挫折の原因になることも少なくありません。
「モチベーション」とは、行動を起こし、それを続けるための意欲や動機のことです。
高すぎる目標は、達成できなかった時の失望感につながり、モチベーションを低下させます。
大切なのは、今の自分にとって少し頑張れば達成できる具体的な目標を設定することです。
例えば、「毎日1時間ウォーキングする」ではなく、「週に2回、会社の昼休みに10分だけ散歩する」「夕食のご飯を半分にする」など、具体的で現実的な目標から始めてみましょう。
目標設定の例は以下の通りです。
| カテゴリ | 目標例 |
|---|---|
| 運動 | エレベーターではなく階段を使う |
| 週に1回、15分ヨガをする | |
| 食事 | 甘い飲み物を水かお茶に変える |
| 週に2回は野菜中心の夕食にする | |
| 睡眠 | 就寝前の30分はスマートフォンを見ない |
| ストレス | 毎日5分間、深呼吸をする時間を作る |

いきなり大きな目標はハードルが高いな…

まずはクリアできそうな小さな目標から始めましょう!
どんなに小さなことでも、目標を達成できれば「できた!」という達成感が得られます。
この小さな成功体験の積み重ねが、自信となり、次のステップへ進むための大きな力となるのです。
行動記録と効果の可視化
日々の努力や体の変化を具体的に記録する行動記録も、モチベーション維持に非常に効果的です。
「記録する」という行為自体が、改善に取り組んでいる意識を高めることにつながります。
例えば、スマートフォンの歩数計アプリで毎日の歩数をチェックしたり、手帳に食べたものや運動した内容をメモしたり、体重や血圧の数値をグラフ化したりすることで、自分の頑張りが目に見える形になります。
体重が少し減った、歩く距離が伸びた、血圧が安定してきたなど、具体的な成果がわかると、達成感とともに「もっと続けよう」という意欲が湧いてきます。
記録におすすめの項目と方法の例を示します。
| 項目 | 記録内容の例 | 可視化の方法例 |
|---|---|---|
| 運動 | 歩数、運動時間、運動内容 | 健康管理アプリ、活動量計 |
| 食事 | メニュー、摂取カロリー、栄養素 | 食事管理アプリ、写真 |
| 睡眠 | 就寝・起床時間、睡眠スコア | 睡眠アプリ、手帳 |
| 体調・測定値 | 体重、体脂肪率、血圧、気分 | 健康管理アプリ、グラフ |

記録するのは少し面倒だけど、効果が見えると嬉しいかも

成果が目に見えると、モチベーションがアップしますよ
記録を続けることで、自分の生活パターンや改善すべき点が客観的に把握できるようになります。
どの行動が効果につながっているのか、あるいは何が妨げになっているのかが明確になり、より効果的な次の行動計画を立てる上でも役立つのです。
周囲の協力、家族との連携
生活習慣の改善は、一人で抱え込まずに、家族やパートナー、友人、職場の同僚など、身近な人の協力を得ることも、継続のための大きな支えとなります。
例えば、パートナーに「健康のために一緒にウォーキングを始めたい」「塩分控えめの食事作りを手伝ってほしい」と具体的な協力をお願いしてみましょう。
また、友人や同僚に「禁煙に挑戦するから応援してほしい」「飲み会では烏龍茶にする」と宣言するのも効果的です。
目標を共有することで、励まし合ったり、時には甘えが出そうな自分を律したりすることができます。
協力をお願いする際のポイントは以下の通りです。
- 自分の目標や、なぜ改善したいのかという想いを伝える
- 「〇〇してほしい」と具体的な協力内容を伝える
- サポートしてくれた時には感謝の気持ちを言葉で伝える
- 相手の負担にならない範囲でお願いする

パートナーにも相談してみようかな

一緒に取り組む仲間がいると心強いですよ
周囲の理解とサポートがあると感じられることは、精神的な安心感につながります。
「頑張っているね」という一言が励みになったり、挫折しそうな時に相談できる相手がいるだけで、困難を乗り越える力が湧いてきたりするものです。
完璧主義を手放す考え方
真面目な方ほど陥りやすいのが、「決めたことは完璧にやらなければならない」という完璧主義の考え方です。
生活習慣改善においては、この完璧主義が、かえって継続を妨げる原因になることが少なくありません。
「毎日必ず運動する」「甘いものは一切食べない」といった厳しいルールを自分に課すと、一度でも守れなかった時に「自分はダメだ」と自己嫌悪に陥り、改善そのものをやめてしまいがちです。
大切なのは、「100点満点を目指さない」という柔軟な考え方を持つことです。
目標の7割か8割程度できていれば十分だと考えましょう。
完璧主義を手放すためのヒントをいくつか紹介します。
- 「今日は疲れているから休もう」「たまには好きなものを食べても良い」と自分を許す
- できなかったことではなく、できたことに目を向けて自分を褒める
- 「まあ、いっか」「明日からまた頑張ろう」と気持ちを切り替える
- 他人と自分の進捗を比べない

全部ちゃんとやらないと、って思いがちだったかも…

少しぐらいできなくても大丈夫。自分を責めないでくださいね
生活習慣の改善は、短距離走ではなくマラソンのようなものです。
一時的に完璧にこなすことよりも、長期的に継続することの方がずっと重要です。
うまくいかない日があっても自分を責めずに、長い目で見て少しずつでも前進していくという意識を持つことが、無理なく続けるための秘訣です。
便利ツールの活用、アプリや情報源
モチベーションの維持や行動の記録には、スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスなどの便利なツールを積極的に活用するのもおすすめです。
近年、健康管理をサポートする様々なツールが登場しており、上手に使えば改善の取り組みをより効果的かつ楽しく進められます。
例えば、Apple WatchやFitbitといったウェアラブルデバイスは、身につけているだけで歩数や消費カロリー、心拍数、睡眠時間などを自動で記録してくれます。
また、「あすけん」や「カロミル」といった食事管理アプリを使えば、食べたものの写真を撮るだけで簡単に栄養計算ができ、食事バランスの改善に役立ちます。
「Sleep Cycle」のような睡眠アプリは、眠りの深さや質を計測し、より良い睡眠のためのアドバイスを提供してくれます。
活用できるツールや情報源の例を以下に示します。
| 種類 | 具体例 | 主な機能・特徴 |
|---|---|---|
| ウェアラブルデバイス | Apple Watch, Fitbit, Garmin | 活動量・睡眠の自動計測、運動記録 |
| 健康管理アプリ | あすけん, FiNC, カロミル | 食事記録・栄養管理、体重・運動記録 |
| 睡眠アプリ | Sleep Cycle, Somnus, Pokémon Sleep | 睡眠サイクル計測、アラーム機能、記録分析 |
| 情報源 | 厚生労働省 e-ヘルスネット, 書籍 | 信頼性の高い健康情報、具体的なノウハウ |

アプリとか使ってみると、ゲーム感覚で続けられるかも?

自分に合ったツールを見つけて、楽しく活用しましょう
これらのツールは、日々の成果をグラフなどで視覚的に示してくれるため、モチベーション向上につながります。
また、目標達成を応援するメッセージ機能や、他のユーザーと交流できるコミュニティ機能を持つアプリもあり、楽しみながら続けられる工夫が凝らされています。
信頼できる情報源から正しい知識を得て、自分に合ったツールを上手に活用することで、生活習慣の改善をよりスムーズに進めることができるでしょう。
よくある質問(FAQ)
- Q忙しくて運動する時間がなかなか取れません。簡単に継続できる運動の具体例はありますか?
- A
エレベーターではなく階段を使う、一駅手前で歩くなど、日常生活の中で意識的に体を動かすことから始めてみましょう。
座りっぱなしの時間を減らし、短い時間でもストレッチや軽い筋トレを取り入れるのも効果的です。
継続することが大切なので、無理のない範囲でできることを見つけるのがポイントになります。
- Q食事の塩分を減らしたいのですが、簡単な方法はありますか? 外食が多いのでメニュー選びのコツも知りたいです。
- A
まずは調味料をかける代わりに「つける」習慣に変えてみませんか。
減塩タイプの調味料を選ぶのも良い方法です。
外食では、定食の汁物は残す、麺類のスープは飲み干さない、野菜の多いメニューを選ぶなどを意識すると塩分を抑えられます。
加工食品を選ぶ際は栄養成分表示をチェックする習慣をつけることも、健康的な食事への第一歩となります。
- Q睡眠の質を高めたいです。寝る前にできる簡単なリラックス方法を教えてください。
- A
就寝90分前までにぬるめのお風呂にゆっくり浸かるのがおすすめです。
また、寝る前の30分はスマートフォンなどを見ず、読書や軽いストレッチ、深呼吸などで心身を落ち着かせる時間を作るのが効果的です。
温かいノンカフェイン飲料を飲むのもリラックスに繋がります。
快適な寝室環境を整えることも睡眠の質向上に役立ちます。
- Q生活習慣の改善を始めても、つい三日坊主になってしまいます。モチベーションを保つための簡単なコツはありますか?
- A
まずは「毎日10分ウォーキングする」「夕食の野菜を1品増やす」など、達成しやすい小さな目標を設定することが大切です。
達成できたら自分を褒めてあげましょう。
歩数や食事内容をアプリなどで記録し、効果を目に見える形にするのもモチベーション維持に繋がります。
完璧を目指さず、できたことに目を向ける考え方も継続の秘訣となります。
- Qストレスがたまると、つい食べ過ぎたり飲みすぎたりしてしまいます。簡単にできるストレス解消法はありますか?
- A
ストレスを感じたときに、飲食以外の解消方法を持っておくことが大切です。
例えば、短い時間でも好きな音楽を聴く、深呼吸をする、軽い運動(ウォーキングやストレッチなど)をする、信頼できる人に話を聞いてもらうなどが挙げられます。
自分に合ったリラックスできることを見つけて、ストレスを溜め込まない習慣をつけましょう。
メンタルケアも健康な生活習慣の一部です。
- Q健康的な食事を心がけたいのですが、毎日のメニューを考えるのが大変です。簡単なレシピや栄養バランスを考えるヒントはありますか?
- A
主食・主菜・副菜を揃えることを意識すると、自然と栄養バランスが整いやすくなります。
主菜は肉や魚、大豆製品などタンパク質を、副菜では野菜をたっぷり摂るように心がけましょう。
具沢山の味噌汁やスープは、手軽に野菜を多く摂れるおすすめメニューです。
レシピアプリや本を参考にしたり、週末に常備菜を作り置きしたりするのも、忙しい平日の食事準備を楽にする方法となります。
まとめ
40代は、将来の健康のために生活習慣を見直す大切な時期です。
この記事では、健康診断の結果や日々の体調の変化に気づき、食事、運動、睡眠、ストレス対処、禁煙・節酒といった具体的な改善策に取り組む方法を解説しました。
特に、無理なく改善を「続ける」ための工夫が重要です。
- 健康診断の結果や日々の体調の変化に気づき、放置するリスクを理解
- 食事(塩分、時間)、運動(日常)、睡眠(質)、ストレス対処、禁煙・節酒の具体的な改善策
- 継続のための小さな目標設定、行動記録、周囲の協力、完璧主義を手放す考え方
- アプリなど便利なツールの活用
この記事を参考に、まずはご自身の生活習慣をチェックし、できそうなことから一つ、小さな目標を立てて始めてみましょう。