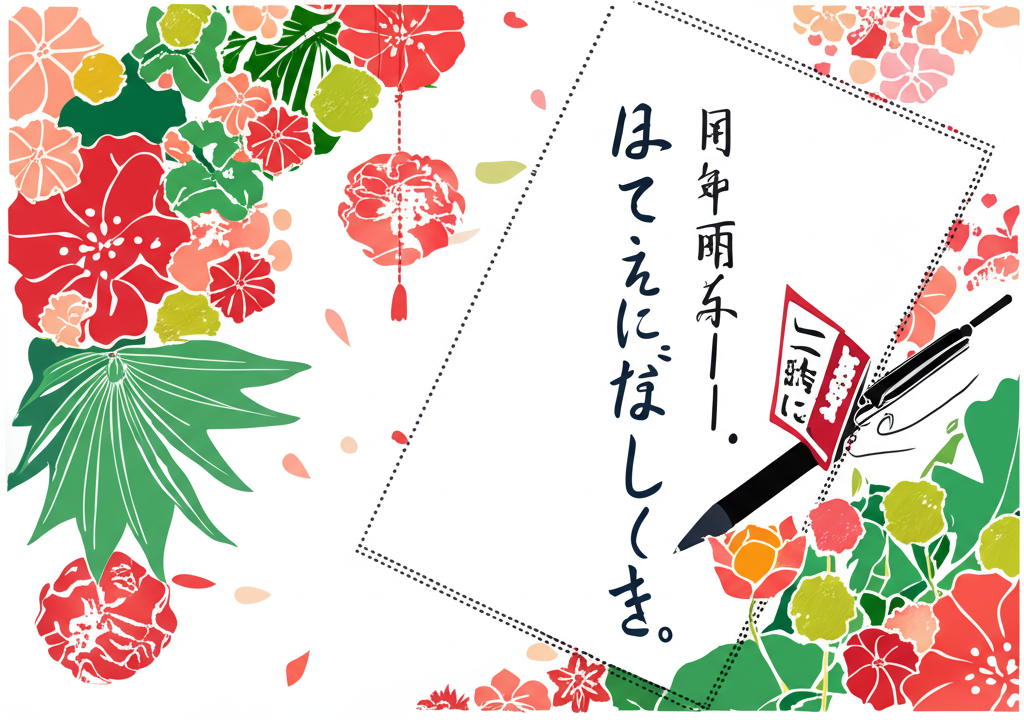新入社員のみなさんにとって、上司への暑中見舞いは日頃の感謝を伝え、良好な関係を築くための大切な機会です。
しかし、初めて送る際は「失礼にならないか」「どう書けばいいのか」と不安に感じることも多いですよね。
特に、正しいマナーを守り、心を込めて作成することが重要になります。
この記事では、新入社員の方が上司へ失礼なく、かつ好印象を与える暑中見舞いを送るための具体的な書き方から基本マナー、デザイン選びのポイントまで、例文を交えながら詳しく解説します。
初めてで不安な方も、この記事を読めば自信を持って準備を進められます。

初めて上司に暑中見舞いを出すけど、書き方やマナーが全然わからなくて不安です…

大丈夫ですよ、この記事で基本からしっかり確認していきましょう
- 新人が上司へ暑中見舞いを送る意義とメリット
- 暑中見舞いの基本マナー5選(時期・はがき・宛名・作成方法・NG内容)
- 失礼なく感謝が伝わる書き方の手順と具体的な例文
- 好印象を与えるデザイン選びと最終チェックのポイント
なぜ送る?新人から上司への暑中見舞いの意義
日頃お世話になっている上司へ暑中見舞いを送ることは、感謝の気持ちを伝え、良好な関係を築く上で大切なコミュニケーション手段となります。
暑中見舞いが持つ本来の意味合いを理解し、新入社員のみなさんが送ることでどのようなメリットが期待できるのかを見ていきましょう。
心を込めて送る一枚のはがきが、今後の仕事にも良い影響を与える可能性があります。
暑中見舞いの本来の意味
暑中見舞いとは、夏の最も暑い時期に、相手の健康を気遣い安否を尋ねるための挨拶状です。
元々は、暑さの厳しい時期に直接相手の家を訪問して見舞う習慣が、時代と共に簡略化され、はがきや手紙を送る形になったといわれています。
厳しい暑さで体調を崩しやすい時期だからこそ、相手を思いやる気持ちを伝える大切な日本の習慣です。

そもそも暑中見舞いってどんなものなの?

夏の暑い時期に相手の健康を気遣う大切な挨拶状ですよ
この本来の意味を理解することで、より心のこもった暑中見舞いを送ることができます。
新人が送るメリットと関係構築への期待
新入社員のみなさんが上司へ暑中見舞いを送ることには、日頃の感謝を形にして伝えられるという大きなメリットがあります。
普段はなかなか改まって伝える機会のない感謝の気持ちや、今後の指導をお願いする言葉を添えることで、上司に真摯な姿勢や礼儀正しさを伝える良い機会になります。
近年、暑中見舞いを送る習慣が薄れているからこそ、新人からの丁寧な挨拶状は上司の印象に残りやすく、「気遣いのできる新人だ」と好意的に受け取ってもらえる可能性が高まります。
また、暑中見舞いがきっかけで上司との会話が生まれ、コミュニケーションが円滑になることも期待できます。

送ったら、上司は喜んでくれるかな?

心を込めてマナーを守って送れば、きっと喜んでいただけますよ
このように、暑中見舞いを送ることは、上司との良好な関係を築き、今後の仕事をスムーズに進めるための一歩となるでしょう。
新人必見!上司への暑中見舞い基本マナー5選
- ① 送る時期の見極め – 梅雨明けから立秋前まで
- ② はがきの選び方 – TPOと涼やかさの意識
- ③ 宛名の正しい書き方 – 敬意を示す基本中の基本
- ④ 手書き?印刷?心を伝えるための選択
- ⑤ 避けるべき内容と言葉遣い – うっかり失礼防止
上司への暑中見舞いは、日頃の感謝を伝える良い機会ですが、マナー違反は避けたいものです。
特に基本的なマナーを押さえることが、相手に失礼なく好印象を与えるための鍵となります。
送る時期の見極めから、はがきの選び方、正しい宛名の書き方、心を伝えるための手書きと印刷の選択、そして避けるべき内容と言葉遣いまで、5つの基本的なマナーをしっかり確認していきましょう。
これらのポイントを押さえれば、初めて暑中見舞いを送る新人の方でも、自信を持って準備を進めることができます。
① 送る時期の見極め – 梅雨明けから立秋前まで
暑中見舞いを送る時期には、明確な目安があります。
「立秋」(りっしゅう)という言葉を聞いたことはありますか。
立秋とは、二十四節気のひとつで、暦の上では秋の始まりとされる日を指します。
暑中見舞いは、一般的に梅雨明け(7月上旬~中旬頃が目安)から、この立秋(例年8月7日頃)の前日までに相手に届くように送るのがマナーです。
立秋を過ぎてしまうと「残暑見舞い」となるため、注意が必要です。
相手の地域によって梅雨明けの時期が異なる場合もありますので、少し余裕をもって準備を始めましょう。

いつまでに送ればいいのでしょうか?

立秋(8月7日頃)の前までに送りましょう
うっかり時期を逃してしまわないよう、カレンダーで立秋の日を確認し、早めに準備に取りかかることをおすすめします。
② はがきの選び方 – TPOと涼やかさの意識
はがき選びも、相手への敬意を示す大切な要素です。
TPO(Time・Place・Occasion:時・場所・場合)をわきまえることが、ビジネスマナーの基本といえます。
上司へ送る暑中見舞いには、一般的な官製はがきか、夏らしい季節感のある私製はがきを選びましょう。
デザインは、受け取った相手が涼やかさを感じられるような、落ち着いたものが好ましいです。
派手すぎるデザインや、ビジネスシーンにふさわしくないキャラクターものは避けるべきです。
| 適切なデザイン例 | 避けるべきデザイン例 |
|---|---|
| 朝顔、ひまわりなどの夏の花 | 派手すぎるイラストや写真 |
| 金魚、風鈴、すだれなど | ビジネスに不適切なキャラクター |
| 海、青空、入道雲など | 全体的に暗い印象のデザイン |
| スイカ、そうめんなど | (関係性によるが)砕けすぎたもの |

どんなデザインのはがきを選べば失礼になりませんか?

涼しげで落ち着いたデザインを選びましょう
心を込めて選んだはがきは、あなたの気遣いを静かに伝えてくれます。
相手が受け取ったときに、心地よい夏の挨拶と感じてもらえるような一枚を選んでみてください。
③ 宛名の正しい書き方 – 敬意を示す基本中の基本
はがきの顔ともいえる宛名は、相手への敬意を最初に示す部分です。
丁寧で正しい宛名書きは、社会人としての基本マナーとして非常に重要となります。
宛名は、はがきの中央に、差出人よりも大きな文字で書くのが一般的です。
会社名、部署名、役職名を省略せずに正確に書き、最後に氏名を書いて「様」をつけます。
自宅住所を知っている場合は自宅宛てに送っても良いですが、不明な場合や迷う場合は会社宛てに送るのが無難です。
住所は都道府県名から書き、マンション名なども省略しないように注意しましょう。
| 送り先 | 宛名書きの例 |
|---|---|
| 会社宛て | 〇〇株式会社(改行)〇〇部(改行)部長 〇〇 〇〇 様 |
| 自宅宛て | (住所)(改行)〇〇 〇〇 様 |

役職名はどのように書けば良いですか?

氏名の前に部署名と役職名を正確に書き、「様」をつけましょう
一文字一文字丁寧に書かれた宛名は、それだけで相手に誠実な印象を与えます。
送る前に誤字脱字がないか、しっかりと確認することを忘れないでください。
④ 手書き?印刷?心を伝えるための選択
心を込めた暑中見舞いを作成する上で、手書きにするか、印刷にするかは悩むポイントかもしれません。
どちらにも良さがあり、一概にどちらが良いとは言えません。
すべて印刷されたはがきでもマナー違反ではありませんが、宛名や本文の最後に一言だけでも手書きのメッセージを添えると、温かみが増し、より丁寧な印象を与えられます。
「今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします」といった簡単な言葉でも、心が伝わるものです。
字に自信がない場合でも、丁寧に書くことを心がければ問題ありません。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 手書き | 気持ちが伝わりやすい、温かみがある | 時間がかかる、書き損じのリスク |
| 印刷 | きれいに仕上がる、効率が良い | 機械的な印象を与える可能性がある |

字に自信がないのですが、印刷だけでは失礼でしょうか?

全て印刷でも問題ありませんが、一言手書きを加えるとより丁寧です
最終的には、あなたの気持ちが相手に伝わることが最も大切です。
手間をかけることが必ずしも良いわけではありませんが、手書きの一手間が、より深い感謝の気持ちを表現することにつながるでしょう。
⑤ 避けるべき内容と言葉遣い – うっかり失礼防止
暑中見舞いの内容は、相手への気遣いを示すものであるべきです。
うっかり失礼な内容や不適切な言葉遣いをしてしまわないよう、細心の注意が必要です。
本文には、仕事の愚痴や不満、個人的すぎるプライベートな話、自慢話といったネガティブな内容は避けるようにしましょう。
また、上司に対して、友人に対するような砕けた言葉遣いや、縁起の悪い「忌み言葉」(例:「終わる」「失う」「倒れる」など)を使うのもマナー違反です。
あくまでも、日頃の感謝と相手の健康を気遣う気持ちを中心に、簡潔にまとめることを心がけてください。
| 避けるべき内容の例 | 避けるべき言葉遣いの例 |
|---|---|
| 仕事の愚痴や会社の批判 | タメ口、若者言葉 |
| 病気や事故などの暗い話題 | 忌み言葉 |
| プライベートな情報の詮索 | 自慢話と受け取られかねない表現 |
| 長すぎる近況報告 | 他人を中傷するような言葉 |

書かない方が良い話題はありますか?

暗い話題や個人的すぎる話、自慢話は避けましょう
相手が気持ちよく受け取れるように、言葉選びや内容には十分に配慮することが大切です。
ポジティブで丁寧な言葉を選び、爽やかな印象の暑中見舞いを完成させてください。
【例文付】失礼なし!上司向け暑中見舞いの作成手順
- ① 構成の基本 – 挨拶から結びまでの流れ
- ② 冒頭の挨拶 – 丁寧な決まり文句の選択
- ③ 本文のポイント – 日頃の感謝と状況の伝え方
- ④ 結びの言葉 – 相手を気遣う定型表現
- ⑤ そのまま使える!感謝が伝わる具体的な文例
暑中見舞いを書く上で、失礼なく気持ちを伝えるためには構成を理解することが最も重要です。
ここでは、① 構成の基本から② 冒頭の挨拶、③ 本文のポイント、④ 結びの言葉、そして⑤ そのまま使える具体的な文例まで、ステップごとに詳しく解説します。
この手順に沿って作成すれば、初めてでも迷うことなく、上司に失礼のない丁寧な暑中見舞いを完成させられます。
① 構成の基本 – 挨拶から結びまでの流れ
暑中見舞いの構成とは、手紙の基本的な流れのことです。
まず①冒頭の挨拶で始まり、②時候の挨拶と相手を気遣う言葉、③本文(日頃の感謝や近況など)、④結びの挨拶、⑤日付、⑥差出人と続くのが一般的です。
| 構成要素 | 内容 | 例文(丁寧な場合) |
|---|---|---|
| ① 冒頭の挨拶 | お見舞いの言葉 | 謹んで暑中お見舞い申し上げます |
| ② 時候の挨拶と気遣う言葉 | 季節の挨拶と相手の健康を気遣う言葉 | 猛暑の候、ますますご健勝のことと… |
| ③ 本文 | 日頃の感謝や近況報告 | 平素は格別のご指導を賜り… |
| ④ 結びの挨拶 | 再度、相手の健康を気遣う言葉 | 暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください |
| ⑤ 日付 | 年と季節 | 令和〇年 盛夏 |
| ⑥ 差出人 | 自分の所属部署と氏名 | 〇〇部 〇〇 〇〇 |

順番通りに書けばいいんですね!

はい、この流れを意識するだけで、まとまりのある文章になりますよ
この基本的な構成を守ることで、相手に失礼なく、かつ内容が伝わりやすい暑中見舞いを作成できます。
② 冒頭の挨拶 – 丁寧な決まり文句の選択
冒頭の挨拶は、暑中見舞いの第一印象を決める重要な部分です。
必ず本文よりも少し大きめの文字で書き始めます。
上司への暑中見舞いでは、「暑中お見舞い申し上げます」が基本ですが、より敬意を示すために「謹んで暑中お見舞い申し上げます」を選ぶと良いでしょう。

「謹んで」を付けた方が丁寧なんですね

その通りです、目上の方への敬意を示す表現として適切ですよ
相手との関係性や状況に応じて適切な表現を選ぶことが、マナーを守る上で大切になります。
③ 本文のポイント – 日頃の感謝と状況の伝え方
本文は、暑中見舞いで最も気持ちを伝えられる部分です。
まず「毎日厳しい暑さが続いておりますが、〇〇部長(様)におかれましてはいかがお過ごしでしょうか」といった時候の挨拶と相手を気遣う言葉から始めましょう。
次に、「平素は格別のご指導ご鞭撻を賜り、心より感謝申し上げます」のように日頃の感謝を具体的に伝えます。
入社して数ヶ月であれば「入社して早3ヶ月が経ち、少しずつ業務にも慣れてまいりました」といった簡単な近況報告を加えるのも良いでしょう。

感謝の気持ちをどう書けばいいか迷います…

具体的なエピソードを少し加えると、より気持ちが伝わりやすくなりますよ
自分の言葉で、正直な感謝の気持ちと前向きな姿勢を示すことが、上司に好印象を与えるポイントです。
④ 結びの言葉 – 相手を気遣う定型表現
結びの言葉は、文章全体を締めくくり、相手への気遣いを改めて示す役割があります。
定型表現として、「暑さ厳しき折、くれぐれもご無理なさらないでください」や「〇〇課長(様)のご健勝と、今後のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます」といった、相手の健康を気遣う言葉を選びましょう。

最後まで気遣いを忘れないようにしないと…

はい、結びまで丁寧に書くことで、全体の印象がぐっと良くなります
季節柄、相手の体調を気遣う一文で締めくくるのが、暑中見舞いのマナーとしてふさわしい形です。
⑤ そのまま使える!感謝が伝わる具体的な文例
ここまで解説した構成とポイントを踏まえ、そのまま使える文例を紹介します。
この例文を参考に、自分の状況や上司との関係性に合わせて適宜修正して活用してください。
特に感謝の言葉は、具体的なエピソードを交えるとより気持ちが伝わります。
markdown
謹んで暑中お見舞い申し上げます
連日厳しい暑さが続いておりますが、〇〇部長におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。
入社して早三ヶ月が経ちましたが、まだまだ未熟でご迷惑をおかけすることも多いかと存じます。
〇〇の業務では、特に丁寧にご指導いただき、誠にありがとうございました。
一日も早く部署に貢献できるよう、精一杯努めてまいりますので、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
暑さ厳しき折から、くれぐれもご自愛くださいませ。
令和〇年 盛夏
(自分の部署名)
(自分の氏名)

この例文を参考にすれば書けそうです!

ぜひ活用してみてください。日付と差出人の記載も忘れないでくださいね
この文例はあくまで一例ですので、あなたの言葉で感謝の気持ちを伝えることが最も大切です。
好印象へ!デザイン選びと心を込める工夫
暑中見舞いにおいて、はがきのデザインやメッセージの工夫は、相手に与える印象を大きく左右します。
特に相手への気遣いを形にすることが、好印象につながる重要なポイントです。
ここでは、夏らしいデザインの選び方、心を込めた手書きメッセージの添え方、そして送る前の最終チェックについて具体的に解説します。
これらの工夫を取り入れることで、上司にあなたの丁寧さや気配りが伝わり、より良い関係を築く一助となります。
夏らしさと気遣いを表現するデザイン選び
はがきのデザインは、受け取った人が最初に目にする部分であり、季節感と相手への配慮を示す大切な要素となります。
定番の朝顔や金魚、風鈴といったモチーフは涼やかさを演出しやすいでしょう。
例えば、郵便局で販売されている夏用のはがきや、文具店で見かける夏柄の私製はがきなど、選択肢は豊富にあります(※注:以前発行されていた「かもめ〜る」は現在販売を終了しています)。
上司の趣味や好みが分かっていれば、それに合わせたデザイン(例:ゴルフ好きの上司なら緑の芝をイメージさせるデザイン)を選ぶのも良い気配りです。
ただし、キャラクターものや派手すぎるデザインは避け、落ち着いた印象のものを選びましょう。

どんなデザインが無難でしょうか?

迷ったら、青や白を基調とした涼しげな色合いで、万人受けする自然(海、山、植物など)のモチーフを選ぶと失敗が少ないです
デザイン選びに迷った際は、涼しげで清潔感のある、万人受けする絵柄を選ぶことが、失礼なく好印象を与えるための確実な方法です。
手書きメッセージの効果的な添え方
全て印刷されたはがきよりも、手書きのメッセージが一言添えられているだけで、温かみと丁寧さが格段に増します。
本文は印刷でも構いませんが、文末に「暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ」や「今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます」といった相手を気遣う言葉や、自身の抱負などを手書きで加えるのが効果的です。
万年筆やボールペン(黒か青インク)を使用し、丁寧に書きましょう。
文字の大きさやバランスにも気を配ると、さらに良い印象を与えます。

字に自信がないのですが、手書きした方が良いですか?

はい、たとえ自信がなくても、丁寧に書かれた文字は気持ちが伝わります。一言だけでも手書きで添えることをおすすめします
手書きの一言は、印刷だけでは伝わらないあなたの誠意を上司に伝えるための、シンプルかつ強力な手段となります。
提出前の最終確認 – 誤字脱字チェックの徹底
どんなに心を込めて作成しても、誤字脱字があっては台無しです。
提出(投函)前の最終確認は、社会人としての基本的なマナーを示す上で非常に重要となります。
特に上司の名前や役職、会社名、部署名に間違いがないかは、最低でも3回は確認しましょう。
「様」の付け忘れなども注意が必要です。
本文の内容はもちろん、日付(令和〇年 盛夏)や自分の名前、住所に間違いがないかも含めて、声に出して読んでみると、見落としを発見しやすくなります。

もし間違えてしまったら、どうすればいいですか?

修正液や修正テープの使用は失礼にあたるため、新しいはがきに書き直すのが最善です
送る前の丁寧なチェックは、あなたの注意力や仕事への真摯な姿勢を示すことにもつながります。
よくある質問(FAQ)
- Q暑中見舞いは、具体的にいつ頃から送り始めるのが適切な時期なのでしょうか?
- A
暑中見舞いを送る適切な時期は、お住まいの地域の梅雨が明けた後からになります。
目安としては、二十四節気の「小暑(しょうしょ)」(7月7日頃)を過ぎたあたりから、「立秋(りっしゅう)」(例年8月7日頃)の前日までに相手へ届くように出すのがマナーです。
送るタイミングを逃さないよう、少し早めに準備を始めましょう。
- Q上司への暑中見舞いをメールで送るのは、ビジネスマナーとして問題ないですか?
- A
暑中見舞いは、本来はがきで送るのが正式なマナーです。
特に新入社員から上司へ初めて送る場合や、礼儀作法を重んじる職場では、はがきを選ぶのが最も丁寧で失礼がない方法です。
会社の文化や上司との関係性によってはメールが許されることもありますが、基本的にははがきで送ることを推奨します。
メールで送りたい場合は、事前に問題ないか確認すると良いでしょう。
- Q暑中見舞いのはがきデザインで、これは絶対に避けるべきというものはありますか?
- A
上司への暑中見舞いでは、ビジネスの場にふさわしくないデザインは避けるべきです。
具体的には、派手すぎる色使いや奇抜なイラスト、子供っぽいキャラクターもの、ご自身のプライベート写真が大きく入ったものなどは不適切です。
また、全体的に暗い印象を与えるデザインも避けましょう。
清潔感があり、涼しさを感じさせる落ち着いたデザインを選ぶのが基本マナーです。
- Q手書きで一言メッセージを添える場合、はがきのどの部分に書くのが最も良いでしょうか?
- A
手書きの一言メッセージは、印刷された本文の後や、はがきの空いているスペースに書き添えるのが一般的です。
本文とは別に、「末筆ではございますが、〇〇様のますますのご健勝をお祈り申し上げます。
」といった結びの挨拶や、日頃の感謝を手書きで加えると、温かみが伝わり丁寧な印象を与えます。
宛名も手書きにすると、より心が込もっていると感じてもらえます。
- Qもし、うっかり立秋(8月7日頃)を過ぎてしまった場合は、どう対応すれば良いですか?
- A
立秋の日を過ぎてしまった場合は、「暑中見舞い」ではなく「残暑見舞い」として送ります。
その際は、冒頭の挨拶を「残暑お見舞い申し上げます」に変更する必要があります。
残暑見舞いは、立秋から8月末までを目安に送るのが一般的です。
送る時期を間違えるのは失礼にあたりますので、立秋の日付を事前に確認しておきましょう。
- Qもし上司から暑中見舞いをいただいたら、返事は必要でしょうか?必要な場合の注意点も教えてください。
- A
上司から暑中見舞いをいただいた際は、お礼の返事を出すのが丁寧なマナーです。
なるべく早く、できればはがきで返信するのが基本です。
もし、すぐに職場などで顔を合わせる機会があれば、直接口頭でお礼を伝えることも可能です。
返信する際には、いただいたことへの感謝の気持ちと、相手の健康を気遣う言葉を必ず添えましょう。
まとめ
この記事では、新入社員のみなさんが上司へ失礼なく、気持ちが伝わる暑中見舞いを送るための方法を詳しく解説しました。
特に基本的なマナーを守り、感謝の気持ちを丁寧に伝えることが大切になります。
- 送る時期(梅雨明け~立秋前)と基本的なマナー(はがき、宛名など)の遵守
- 失礼のない構成と心を込めた感謝の言葉の選択
- 夏らしさと気遣いを表現するデザイン選びと手書きの工夫
- 提出前の誤字脱字チェックの徹底
この記事で解説したポイントや具体的な例文を参考に、自信を持って上司への暑中見舞いを準備してください。