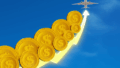オリックスの株価は、高い配当利回りが魅力ですが、事業内容の複雑さや株主優待の廃止で、投資に踏み切るべきか迷いますよね。
この記事では、アナリストの客観的な評価や将来性を踏まえ、オリックス株が「買い」なのかどうかを判断するための材料を徹底的に解説します。
「万年割安株」と評価されてきた理由や、株主優待廃止後の新しい株主還元策、そして新NISAを活用した具体的な買い方まで、投資判断に必要な情報を網羅的に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

株主優待がなくなるし、本当に今が買い時なのかな?

優待廃止の費用は今後の増配に充てられるため、高配当株としての魅力はむしろ高まっています
- オリックスの今後の株価見通しとアナリストの評価
- 株価が「万年割安」と評価される理由
- 株主優待廃止後の配当方針と利回り
- 新NISAを活用したオリックス株の買い方
オリックスの株価は割安?今後の見通しを分析
オリックスの株価は「万年割安」と耳にすることもあり、本当に投資して大丈夫なのか不安になりますよね。
しかし、その背景をきちんと理解すれば、むしろ魅力的な投資機会であることがわかります。
今後の見通しを、事業内容や専門家の評価といった多角的な視点から分析していきましょう。
| 分析の切り口 | ポイント |
|---|---|
| 最新の株価・チャート | 長期的な株価推移から企業の安定性を確認 |
| 事業内容 | 収益の柱が分散されたコングロマリット経営の強み |
| アナリスト予想 | 専門家による客観的な評価と目標株価 |
| 割安な理由 | 「コングロマリット・ディスカウント」という評価の背景 |
| 好材料と懸念材料 | 今後の株価を左右するプラス・マイナス要因 |
このセクションでは、オリックスがなぜ割安と評価されるのか、そして将来性はどうなのかを深掘りします。
これらのポイントを一つひとつ確認することで、安心して投資判断ができるようになります。
最新のオリックス株価と10年チャートの推移
現在の株価水準だけでなく、長期的な視点でのパフォーマンスを把握することが、銘柄の本当の実力を見極める上で欠かせません。
短期的な価格の上下に一喜一憂せず、大きな流れを捉えることが大切です。
2024年6月時点のオリックスの株価は約3,500円前後で推移しており、PBR(株価純資産倍率)は長年の課題であった1倍をわずかに超える約1.1倍で取引されています。
10年間の株価チャートを振り返ると、コロナショックで一時1,200円台まで下落する場面もありましたが、その後は力強く回復し、右肩上がりの成長軌道を描いていることが確認できます。

最近の株価の動きだけ見ていると、判断を間違えそう…

はい、短期的な値動きだけでなく、10年単位の長期チャートで全体像を把握することが大切です。
日経平均株価と比較しても、オリックスの株価は安定したパフォーマンスを示してきました。
これは、後述する多角的な事業基盤が、経済の変動に対する抵抗力を持っていることの証左です。
オリックスはどんな会社?多角的な事業内容
オリックスと聞くとリース会社のイメージが強いかもしれませんが、それは事業の一面に過ぎません。
現在のオリックスは、リース事業で培った知見を活かし、多角的な事業を展開するコングロマリット(複合企業)へと進化を遂げています。
具体的には、法人金融、産業/ICT機器、不動産、環境エネルギー、保険、銀行、自動車関連、事業投資など10のセグメントで事業を展開しています。
2024年3月期の決算では、海外部門の利益が全体の約4割を占めるなど、グローバルでの収益力も高まっています。
この収益源の多様性が、オリックスの経営を安定させているのです。

結局、何で稼いでいる会社なの?

リースが祖業ですが、今では10の事業の柱があり、収益源が分散されているのが強みです。
一つの事業が不調でも、他の事業がカバーする。
このようなビジネスモデルによって、オリックスは特定の業界の景気変動に左右されにくい、安定した収益基盤を築き上げています。
アナリスト予想から見るオリックス株価の今後
自分一人の判断だけでなく、専門家の意見を参考にすることも投資戦略において有効です。
証券会社のアナリストが公表するレーティング(投資判断)は、企業の将来性を客観的に評価する上で役立つ指標となります。
「みんかぶ」の集計によると、2024年6月時点で10名のアナリストのうち9名が「買い」以上の強気な評価をしています。
アナリストが設定する目標株価の平均値も4,000円を超えており、現在の株価からの上昇余地が期待されている状況です。
これは、PBR1倍超えに向けた自社株買いといった株主還元策や、今後の事業成長が高く評価されていることを示しています。

専門家はどう見ているんだろう?

多くのアナリストは、現在の株価よりも高い目標を設定し、強気の姿勢を示しています。
もちろん、アナリストの予想が必ず当たるわけではありません。
しかし、多くの専門家がポジティブな見方をしているという事実は、投資を検討する上で心強い判断材料の一つとなります。
オリックスの株価が割安(万年割安)な理由
オリックスの株価が業績や資産価値に比べて割安な水準で評価されてきた背景には、「コングロマリット・ディスカウント」という現象があります。
これは、事業内容が多岐にわたるため、投資家から「何をやっている会社か分かりにくい」と見なされ、本来の企業価値よりも株価が低く評価されてしまう状態を指します。
事実、オリックスのPBRは長年にわたって1倍を割り込む状態が続いていました。
ようやく最近になって1倍を回復しましたが、同業他社と比較すると、まだ割安感が残っていることがわかります。
| 会社名 | PER(株価収益率)の目安 | PBR(株価純資産倍率)の目安 |
|---|---|---|
| オリックス | 約10倍 | 約1.1倍 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 約13倍 | 約0.9倍 |
| 三井物産 | 約12倍 | 約1.6倍 |
他の大手金融機関や総合商社と比較しても、オリックスの株価指標は魅力的な水準にあります。
この「分かりにくさ」ゆえの割安感は、企業の実態を理解している投資家にとっては、むしろ絶好の投資機会と捉えることができます。
今後の株価に影響する好材料と懸念材料
オリックスへの投資を判断する際は、将来の株価を動かすプラス要因とマイナス要因の両方を冷静に見ておく必要があります。
好材料と懸念材料を天秤にかけ、総合的に判断することが、長期的な成功につながります。
今後のオリックスの株価に影響を与えうる主な要因を、以下の表に整理しました。
| 分類 | 主な要因 |
|---|---|
| 好材料 | ・国内の金利上昇による金融事業の収益改善 ・PBR改善に向けた積極的な自社株買いや増配 ・再生可能エネルギー事業や海外M&Aによる持続的成長 |
| 懸念材料 | ・世界的な景気後退による事業環境の悪化 ・国内外の不動産市況の変動リスク ・大型M&A(企業の合併・買収)戦略の成否 |

良い話ばかりじゃないよね?リスクも知りたい。

はい、金利上昇のような追い風もありますが、世界景気の後退といった向かい風も想定しておく必要があります。
現状では、世界経済の動向に注意が必要な一方、金利上昇という追い風や、企業価値向上に向けた経営陣の強い意志が株価を支えると考えられます。
これらの材料を継続的にチェックしていくことが重要です。
オリックス株価の魅力!高配当と株主還元策
株主優待の廃止は一部の投資家にとって残念なニュースですが、オリックスの本当の魅力は、企業の成長を株主にしっかりと還元する利益還元への強い姿勢にあります。
優待廃止によって、その資金が配当へ振り向けられることで、高配当株としての魅力はむしろ高まったと捉えることができます。
これから、株主優待の廃止がもたらす影響や、実績に裏付けられた高い配当利回り、そして実際に株主になるために必要な資金について、一つずつ確認していきましょう。
【重要】株主優待の廃止と今後の株主還元策
オリックスは、個人投資家から人気を集めていたカタログギフト「ふるさと優待」を、2025年3月31日時点の株主名簿への記載をもって廃止することを決定しました。
この変更の背景には、国内の機関投資家や海外投資家を含めた、すべての株主に対して公平な利益還元を追求するという企業の方針があります。
会社側は、株主優待制度にかかっていたコストを配当金の増額、つまり「増配」の原資に充てることを明確に示しています。

株主優待がなくなるのは、やっぱり残念だな…

優待廃止は、今後のさらなる増配への期待が高まるポジティブなニュースと捉えることもできますよ
優待がもらえる最後の機会を狙うのであれば、2025年3月末の権利付き最終日までにオリックス株を保有することが必要です。
オリックスの配当金はいつ?権利確定日まとめ
オリックスの配当金を受け取る権利を得るために重要な日、それが権利確定日です。
この日に株主名簿に名前が記載されていれば、配当金を受け取れます。
オリックスは、毎年3月末に期末配当、9月末に中間配当と、年に2回配当を出します。
配当金を受け取るには、それぞれの権利確定日から2営業日前の「権利付最終売買日」までに株式を購入しておく必要があります。

いつまでに株を買えば、いつ頃配当金がもらえるのだろう?

権利確定日の2営業日前までに購入すれば、約2〜3ヶ月後に受け取れます
| 項目 | 中間配当 | 期末配当 |
|---|---|---|
| 権利確定月 | 9月末 | 3月末 |
| 権利付最終売買日(目安) | 9月の最終営業日の2営業日前 | 3月の最終営業日の2営業日前 |
| 配当金支払時期(目安) | 12月上旬ごろ | 6月下旬ごろ |
例えば、2025年3月末の期末配当を得たい場合、権利付最終売買日である2025年3月27日(木)までにオリックスの株式を購入することが求められます。
ご自身の投資計画に合わせて、購入のタイミングを検討しましょう。
驚異の増配率!配当利回りと配当金の推移
オリックスの株主になる最大のメリットは、安定して配当を出し続ける株主還元の方針です。
リーマンショックのような特別な経済危機を除き、減配をせずに配当を維持、または増やす「累進配当」に近い考え方を採用しています。
その実績は数字にも表れており、2024年3月期の年間配当金は1株あたり94円で、過去10年間で配当額は約5倍にまで増加しました。
株価に対する配当利回りも高い水準を維持しており、長期で資産形成を目指す投資家にとって大きな魅力になっています。
| 決算期 | 1株あたり年間配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2021年3月期 | 78円 | 49.6% |
| 2022年3月期 | 85.6円 | 30.1% |
| 2023年3月期 | 85.6円 | 33.1% |
| 2024年3月期 | 94円 | 29.5% |
| 2025年3月期(予想) | 98.6円 | 約33% |
このように実績ある増配の歴史は、オリックスの安定した収益力と、株主を大切にする姿勢の証明と言えるでしょう。
オリックスの株を100株買うのにいくら必要?
「オリックスの株主になってみたいけれど、一体いくら準備すれば良いのだろう」と考える方もいるでしょう。
オリックス株は100株単位で購入でき、必要な資金は「現在の株価 × 100株」という簡単な式で計算できます。
例えば、株価が1株3,500円のタイミングであれば、3,500円 × 100株で、最低投資金額は350,000円です。
この金額は、最新のノートパソコン1台分や、少し豪華な国内旅行の費用に相当します。

30万円以上となると、まとまったお金が必要ですね

新NISAの成長投資枠(年間240万円)を使えば、非課税で効率的に始められますよ
この投資金額に加えて、実際に株を購入する際には、証券会社へ支払う少額の売買手数料がかかることを覚えておきましょう。
オリックス株の買い方とおすすめネット証券
オリックス株を購入する手続きは、証券会社の口座があれば誰でも簡単に行えます。
特に、投資で得た利益(配当金や売却益)が非課税になる新NISAの「成長投資枠」を利用するのが断然おすすめです。
これから株式投資を始める方には、スマートフォンやパソコンから手軽に口座を開設でき、取引手数料も安いネット証券が適しています。
SBI証券、楽天証券、マネックス証券の3社は、多くの投資家に利用されており、初心者でも使いやすいサービスを提供しています。
| 証券会社 | 特徴 | NISAでの国内株手数料 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 総合力No.1。TポイントやVポイントなどが貯まる | 無料 |
| 楽天証券 | 楽天経済圏との相性抜群。楽天ポイントが貯まる・使える | 無料 |
| マネックス証券 | 米国株に強い。銘柄分析ツールが充実 | 無料 |
口座開設は無料で完了しますので、まずはご自身に合った証券会社を選び、オリックス株を購入する第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
よくある質問(FAQ)
- Qオリックスの銘柄コードは何ですか?
- A
オリックスの銘柄コードは「8591」です。
証券会社のアプリやサイトで株価を検索する際に、この番号を入力するとスムーズに銘柄情報を見つけられます。
- Q業績が悪くなったら、配当金が減る可能性はありますか?
- A
オリックスは減配をせず、配当を維持または増やす「累進配当」に近い方針を掲げています。
実際にリーマンショックのような大きな経済危機を除き、減配していない実績があります。
そのため、配当金が大きく減るリスクは比較的低いと考えられます。
- Q話題のカタログギフトがもらえる最後のチャンスはいつですか?
- A
カタログギフト(ふるさと優待)がもらえるのは、2025年3月31日時点の株主名簿に記載されている株主が対象です。
そのためには、権利付き最終日(通常は3月末の2営業日前)までに株を保有する必要があります。
これが株主優待を受け取れる最後の機会になるでしょう。
- Qオリックスの株価が「万年割安」なのは、今後も続きますか?
- A
事業が多角的なため「コングロマリット・ディスカウント」で株価が割安と評価されがちでした。
しかし、会社側もこの状況を課題と捉え、積極的な自社株買いや増配を進めています。
これらの株主還元策が市場に評価されれば、割安な状態は徐々に解消されていくと期待できます。
- Q新NISAでオリックス株に投資するメリットは何ですか?
- A
最大のメリットは、受け取る配当金が非課税になることです。
通常、配当金には約20%の税金がかかりますが、新NISAの「成長投資枠」で購入すると、その税金がかからなくなります。
配当金の魅力を最大限に活かせるため、個人投資家には特におすすめの方法です。
- Q株価が大きく下がるようなリスクや注意すべき点はありますか?
- A
どのような株式にも価格が変動するリスクはあります。
オリックスの場合、特に注意すべきは世界的な景気の後退です。
事業が世界中に広がっているため、海外の経済や不動産市況の悪化が業績に影響を与える可能性があります。
投資を判断する際は、これらの点も考慮に入れることが大切です。
まとめ
この記事では、オリックスの株価について、今後の見通しや株主還元の魅力を解説しました。
オリックスは事業内容の複雑さから株価が割安に評価されがちですが、株主優待の廃止資金を増配に充てるなど、株主への利益還元に非常に積極的な企業です。
- 株主優待に代わる増配など、積極的な株主還元姿勢
- 多角的な事業がもたらす安定した収益基盤と割安な株価
- 専門家(アナリスト)による高い評価と今後の成長への期待
- 新NISA活用による配当金の非課税メリット
高配当株としての魅力が増しているオリックスは、長期的な資産形成を目指す上で有力な選択肢となります。
この記事で投資に興味を持った方は、まずは配当金のメリットを最大限に活かせる新NISA口座の活用から検討してみてください。