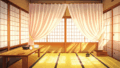70代になると、弔事の席に参列する機会が増え、喪服について考える場面が多くなります。
故人を偲び、ご遺族への敬意を表す心遣いとして、マナーを守りつつ、ご自身に合った快適な喪服を選ぶことが大切です。
この記事では、日本の伝統的な喪服のマナーを踏まえつつ、70代の女性が気品を保ちながらも体型や着心地に配慮した最適な一着を見つけるためのポイントを、デザイン、素材、小物選び、購入・レンタルの判断基準まで分かりやすく解説いたします。

今の私に合う喪服って、どう選べばいいのかしら…

この記事を読めば、マナーも着心地も安心の一着が見つかりますよ
- 70代向け喪服の基本マナー
- 体型や快適さを考慮したデザイン・素材の選び方
- 失敗しない小物選びのポイント
- 購入とレンタルの判断基準
70代喪服選びの基本:マナーと格式の理解
- 喪服の種類と格式の基本(正喪服・準喪服・略喪服)
- 立場に応じた格式の選び方(喪主・近親者・一般参列者)
- 場面に応じた適切な服装(お通夜・葬儀・法事)
- 近年の傾向:準喪服の一般化と注意点
- 「平服でお越しください」への対応
喪服を選ぶ上で最も重要なのは、故人への敬意を示すためのマナーと、場にふさわしい格式を理解することです。
立場や場面に合わせた適切な装いを心がけることが、弔意を表す第一歩となります。
ここでは、喪服の基本的な種類と格式、故人との関係性(立場)に応じた選び方、お通夜や葬儀、法事といった場面ごとの服装、近年の傾向、そして「平服でお越しください」と案内された場合の対応について、順に解説します。
これらの基本を押さえることで、どのような弔事の場面でも戸惑うことなく、自信を持って適切な装いを選ぶことができます。
喪服の種類と格式の基本(正喪服・準喪服・略喪服)
喪服には、格式の高い順に「正喪服(せいもふく)」「準喪服(じゅんもふく)」「略喪服(りゃくもふく)」という3つの種類が存在します。
これは、故人への敬意の度合いや場面に応じて使い分けるものです。
正喪服が最も格式高く、次に準喪服、そして略喪服と続きます。
一般的に「喪服」として広く着用されるのは準喪服です。
| 種類 | 格式 | 主な着用者 | 主な着用場面 | 女性の服装例 (洋装) |
|---|---|---|---|---|
| 正喪服 | 最も高い | 喪主、三親等以内の親族 | 葬儀・告別式、一周忌までの法要 | 肌露出や装飾を抑えた上質なブラックフォーマルアンサンブル等 |
| 準喪服 | 一般的 | 一般参列者、喪主・親族も着用増 | お通夜、葬儀・告別式、多くの法事 | ブラックフォーマル(ワンピース、アンサンブル、スーツ等) |
| 略喪服 | 控えめ | 一般参列者 | 急なお通夜、三回忌以降の法事、お別れの会、平服指定時 | 黒や濃紺等の地味な色のワンピース、スーツ、アンサンブル |
まずは、この3つの種類と格式の違いを理解することが、適切な喪服選びの第一歩となります。
立場に応じた格式の選び方(喪主・近親者・一般参列者)
喪服の格式選びで重要なのは、故人との関係性、つまりご自身の「立場」です。
喪主やご遺族側か、それとも一般の参列者かによって、ふさわしいとされる服装の格式が変わります。
一般的に、参列者は喪主側よりも格式を高くしないように配慮することが大切です。
| 立場 | 主な着用場面 | 推奨される服装 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 喪主・三親等以内の親族 | 葬儀・告別式、一周忌まで | 正喪服 または 準喪服 | 近年は準喪服が主流。和装の場合は地域の慣習確認 |
| 喪主・三親等以内の親族 | お通夜、三回忌以降の法事 | 準喪服 または 略喪服 | |
| 一般参列者 | お通夜、葬儀・告別式、一周忌・三回忌まで | 準喪服 | 急なお通夜の場合は略喪服でも可 |
| 一般参列者 | 三回忌以降の法事、「平服」指定の場合 | 略喪服 (迷う場合は準喪服でも可) |
故人との関係性をふまえ、失礼のない格式の喪服を選びましょう。
場面に応じた適切な服装(お通夜・葬儀・法事)
喪服は、参列する弔事の「場面」によっても適切な装いが異なります。
お通夜、葬儀・告別式、そして回忌を重ねる法事では、求められる服装の格式が変わることがあります。
特に一般参列者の場合は、場面に応じた服装を心がけましょう。
| 場面 | 推奨される服装 (一般参列者の場合) | 補足 |
|---|---|---|
| お通夜 | 準喪服 または 略喪服 | 急ぎ駆けつける場合は略喪服でも可。近年は準喪服が一般的 |
| 葬儀・告別式 | 準喪服 | 最も格式が重んじられる場。略喪服は避ける |
| 初七日~一周忌 | 準喪服 | |
| 三回忌 | 準喪服 または 略喪服 | 迷う場合は準喪服が無難 |
| 七回忌以降 | 略喪服 | 「平服」の案内があればそれに従う。より簡略化される傾向 |
参列する儀式の種類に合わせて、適切な服装を選ぶことが肝心です。
近年の傾向:準喪服の一般化と注意点
かつての厳格なルールから、近年、喪服の着用習慣には変化が見られます。
特に注目すべきは、「準喪服」の一般化です。
以前は喪主や近親者は正喪服を着るのが正式とされていましたが、和装の準備の手間や洋装正喪服の入手の難しさから、現在では喪主側でも準喪服(ブラックフォーマル)を着用するケースが非常に増えています。
この傾向から、質の良い準喪服を一着用意しておけば、ほとんどの弔事に対応でき、70代の方にとっても現実的で安心な選択肢といえるでしょう。
お通夜に関しても、以前は「急いで駆けつけた」という意味合いから略喪服が推奨されましたが、現在では準喪服での参列が一般的になっています。
「平服でお越しください」への対応
法事の案内などで「平服(へいふく)でお越しください」と書かれている場合があります。
これは「普段着で良い」という意味ではありませんので注意が必要です。
この場合の「平服」とは、基本的には「略喪服」を指します。
黒や濃紺、ダークグレーといった地味な色のワンピースやスーツ、アンサンブルを選びましょう。

「平服で」って言われると、何を着ていけばいいか一番迷うのよね…

大丈夫です。普段着ではなく、控えめな服装=略喪服と考えれば安心ですよ。
もし服装に迷う場合は、控えめなデザインの準喪服を着用しても失礼にあたることは少ないです。
ただし、正喪服のような格式の高い服装は場違いになる可能性があるため避けるべきです。
品格と快適性を両立するデザイン・素材・機能性の選び方
- 体型をカバーし品良く見せるシルエット
- 年齢にふさわしいスカート丈と袖丈の目安
- 襟元デザインと控えめな装飾のポイント
- パンツスーツという選択肢とその注意点
- 深い黒(漆黒)と上質な素材感の重要性
- 季節に合わせた素材選び(夏・冬・通年)
- 着脱しやすい前開きファスナーなどの便利機能
- 締め付けを軽減する工夫と動きやすさ
- 自宅で洗えるなどお手入れのしやすさ
70代の喪服選びでは、マナーを守ることと同等に、ご自身の体型や変化に合わせた着心地の良いデザインや素材を選ぶことが重要になります。
体型カバーを意識したシルエットや適切な丈、安心感のある襟元、パンツスーツの検討、素材の色や質感、季節への対応、そして着脱のしやすさや動きやすさといった機能面まで、品格と快適性を両立するための具体的なポイントを見ていきましょう。
年齢を重ねたからこその落ち着きと、無理のない快適さを両立できる喪服を選びましょう。
体型をカバーし品良く見せるシルエット
体型カバーで重要なのは、体のラインを拾いすぎない、ほどよいゆとりのあるシルエットを選ぶことです。
例えば、お腹周りが気になる方には、ウエスト部分からふんわり広がるAラインのワンピースや、ジャケットの裾にデザイン性のあるペプラム仕様などがおすすめです。
締め付け感がなく、かつ上品な印象を与えます。

お腹周りが少し気になるのだけど…

体のラインを拾いすぎないデザインを選ぶと安心です
ご自身の気になる部分を自然にカバーし、長時間でも楽に過ごせるシルエットを選びましょう。
年齢にふさわしいスカート丈と袖丈の目安
品位を保つ上で、スカート丈と袖丈は特に注意したいポイントです。
スカート丈は、最低でも膝が完全に隠れる「膝下丈」、できればふくらはぎの中ほどからくるぶし近くまでの「ミディ丈」や「ロング丈」を選ぶと、落ち着いた印象になります。
椅子に座った際にも膝頭が見えない長さが良いでしょう。
袖丈は、季節を問わず長袖が最も正式ですが、夏場や準喪服であれば肘がしっかり隠れる五分袖や七分袖も一般的になっています。
| 項目 | 推奨される長さ | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| スカート丈 | 膝下丈、ミディ丈、ロング丈 | 座った時に膝が見えない、落ち着いた印象 |
| 袖丈 | 長袖(最も正式)、五分袖・七分袖(肘が隠れる) | 肌の露出を抑える、夏場は通気性も考慮 |
肌の露出を控え、落ち着きと品格を感じさせる丈を選ぶことが大切です。
襟元デザインと控えめな装飾のポイント
襟元のデザインは、顔周りの印象を左右し、フォーマル感を高める要素です。
開きすぎない、詰まったデザインが基本となります。
首元がすっきりと見えるスタンドカラー(立ち襟)や、上品なラウンドネック、ボートネックなどが適しています。
胸元が大きく開いたデザインは避けましょう。
装飾は基本的にない方が望ましいですが、準喪服であれば、共布の小さなリボンやフリル、ピンタック、部分的なレース使いなど、目立たない控えめなものであれば許容される場合があります。
光沢のある素材や大きな飾りは避けることが重要です。

少しデザインがあった方がおしゃれかしら?

装飾は控えめに、あくまで上品さを意識しましょう
首元の詰まったデザインを選び、装飾はごく控えめなものに留めることで、品格を保つことができます。
パンツスーツという選択肢とその注意点
近年、喪服としてパンツスーツを選ぶ方が増えています。
特に70代の方にとっては、動きやすさや安心感の面でメリットがあります。
パンツスーツは、立ったり座ったりの動作が楽で、足元が冷えやすい方には保温効果も期待できます。
足さばきが良く、転倒防止にもつながります。
ただし、選ぶ際には注意点があります。
必ず「ブラックフォーマル」として販売されている喪服専用のパンツスーツを選んでください。
ビジネス用の黒いパンツスーツは色味や素材感が異なるため不適切です。
また、スカートスタイルに比べるとやや略式と見なされる可能性があるため、一般参列者としての着用は問題ありませんが、立場によっては慎重な判断が求められます。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 動きやすい、足さばきが良い | 必ず「ブラックフォーマル(喪服)」用を選ぶ |
| 転倒防止につながる | ビジネス用の黒パンツスーツはNG |
| 保温性が高い(特に冬場) | スカートに比べ略式と見なされる可能性あり(立場によっては要検討) |
| 体型カバー効果 |
動きやすさや保温性を重視する場合、マナーを守った喪服用のパンツスーツは有効な選択肢となります。
深い黒(漆黒)と上質な素材感の重要性
喪服を選ぶ上で最も重要な要素の一つが、色の深さと素材の質感です。
弔事の場にふさわしい、光沢のない深い黒、「漆黒(しっこく)」を選ぶことがマナーの基本となります。
一般的な黒い衣服と喪服用の黒は、「濃染加工(のうせんかこう)」という特別な染色が施されているため、並べてみると色の深みが全く異なります。
安価なものだとテカリがあったり、グレーっぽく見えたりすることがあります。
素材は、ウールや高品質なポリエステルなどが一般的で、マットで落ち着いた質感のものを選びましょう。
サテンのような光沢のある素材は基本的に避けるべきです。

普通の黒い服じゃだめなの?

喪服用の深い黒色と、上質な素材感を確認しましょう
品格を表現するためにも、光沢のない深い黒色と、安っぽく見えない上質な素材感にこだわりましょう。
季節に合わせた素材選び(夏・冬・通年)
喪服は長時間着用することも多いため、季節に合った素材を選ぶことで、快適さが大きく向上します。
基本となるのは、ジャケットとワンピース(またはブラウス)がセットになったオールシーズン対応のアンサンブルです。
これ一着あれば多くの場面に対応できます。
夏の暑い時期には、通気性の良い薄手の生地や、接触冷感機能を持つ素材を使用した夏用の喪服も販売されています。
袖丈はマナーを守りつつ五分~七分袖を選ぶと良いでしょう。
冬の寒い時期には、ウール混など保温性の高い素材が適しています。
見えない部分で保温下着を着用したり、パンツスーツを選んだりするのも有効な防寒対策です。
| 季節 | 素材・機能性のポイント | 服装の例 |
|---|---|---|
| 通年 | シーズン問わず着用可能、汎用性が高い | ポリエステル等のアンサンブル |
| 夏 | 通気性、吸湿速乾性、接触冷感など | 夏用生地のワンピース、五分・七分袖アンサンブル |
| 冬 | 保温性(ウール混など)、防寒対策 | 暖かい素材のアンサンブル、パンツスーツ |
季節に応じた素材を選ぶことで、暑さや寒さによる不快感を軽減し、儀式に集中しやすくなります。
着脱しやすい前開きファスナーなどの便利機能
年齢を重ねると、腕が上がりにくくなったり、背中のファスナーに手が届きにくくなったりすることがあります。
着脱のしやすさは、喪服選びにおいて見逃せないポイントです。
特に便利なのが、ワンピースの前面にファスナーが付いている「前開き」デザインです。
これなら、腕を後ろに回す必要がなく、一人でも楽に着たり脱いだりすることが可能です。
シニア向けの喪服では、この前開きタイプが多く見られます。
試着の際には、実際にファスナーの開け閉めがスムーズにできるか確認すると良いでしょう。

背中のファスナーが苦手で…

前開きファスナーのワンピースなら着替えがとても楽ですよ
前開きファスナーのような便利な機能が付いた喪服を選ぶことで、着替えの際のストレスを大幅に減らすことができます。
締め付けを軽減する工夫と動きやすさ
長時間座っていることの多い弔事では、体を締め付けない工夫や動きやすさが、疲労感を軽減する上で重要になります。
ウエスト部分にゴムを使用しているスカートやパンツは、お腹周りの圧迫感が少なく快適です。
また、腕を動かしやすいように、アームホール(袖ぐり)にゆとりを持たせたデザインや、多少のストレッチ性がある素材(フォーマル感を損なわないもの)なども、動きやすさにつながります。
立ったり座ったり、お辞儀をしたりといった動作がスムーズに行えるか、試着時に確認しましょう。
| 工夫のポイント | 具体例 |
|---|---|
| ウエスト周りの快適性 | ウエストゴム仕様のスカート・パンツ |
| 腕周りの動かしやすさ | ゆとりのあるアームホール(袖ぐり) |
| 全体の動きやすさ | ストレッチ性のある素材(フォーマル感は維持) |
| シルエット | 体を締め付けないゆったりとしたデザイン |
体への負担が少ない、締め付け感のないデザインや素材を選ぶことで、長時間でも楽に過ごすことができます。
自宅で洗えるなどお手入れのしやすさ
喪服は頻繁に着るものではありませんが、着用後は清潔に保ちたいものです。
お手入れのしやすさも、選ぶ際のポイントになります。
近年、自宅の洗濯機で洗える「ウォッシャブル」タイプの喪服が増えています。
クリーニングに出す手間や費用を考えると、自宅で手軽にお手入れできるのは大きなメリットです。
特に夏場など汗をかきやすい季節には重宝します。
ただし、洗濯が可能かどうかは、必ず洗濯表示を確認してください。
上質な素材のものはドライクリーニングのみの場合もあります。

クリーニングに出すのが面倒で…

自宅で洗えるタイプならお手入れが簡単です
ご自身のライフスタイルに合わせて、お手入れがしやすい喪服を選ぶことも検討しましょう。
失敗しない小物選び:バッグからアクセサリーまで完全ガイド
- バッグの選び方:素材・デザイン・サブバッグ
- 靴の選び方:素材・デザイン・ヒールの高さ
- アクセサリーのマナー:パールネックレス・イヤリング/ピアス・指輪
- ストッキングの色と厚さの基本ルール
- ハンカチ・袱紗(ふくさ)・数珠(じゅず)の準備
- 冬場のコート選びと注意点
- 髪型・メイク(片化粧)・ネイルの整え方
喪服の装いでは、服装本体だけでなく、合わせる小物選びも故人やご遺族への敬意を示す大切な要素です。
バッグや靴、アクセサリー、その他の持ち物にも、それぞれ守るべきマナーがあります。
ここでは、バッグ、靴、アクセサリー、ストッキング、ハンカチ・袱紗・数珠、冬場のコート、そして髪型・メイク・ネイルといった、喪服に合わせる小物や身だしなみのポイントを詳しく解説していきます。
細部まで心を配ることで、より一層心のこもった装いとなります。
バッグの選び方:素材・デザイン・サブバッグ
喪服に合わせるバッグは、光沢のない黒い布製が最も基本とされています。
殺生を連想させる革製品は避けるのが無難ですが、もし使用する場合は、凹凸のないマットな質感のシンプルなものを選びましょう。
デザインは、大きな金具やブランドロゴが目立たない、小ぶりなハンドバッグタイプが適しています。
ショルダーバッグやトートバッグはカジュアルに見えるため、弔事の場にはふさわしくありません。
| 項目 | 推奨されるもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|
| 色 | 黒 | 黒以外 |
| 素材 | 布製(基本)、マットな革(シンプルなもの) | 光沢素材(エナメル等)、爬虫類系、毛皮、派手な柄 |
| デザイン | 小ぶりなハンドバッグ、金具やロゴが目立たない | ショルダー、トート、リュック、大きな金具・ロゴ |
| その他 | – | ビーズやスパンコールなどの装飾 |

荷物が多くてハンドバッグに入りきらない場合はどうしたら良いですか?

その場合は、黒無地で光沢のないシンプルなサブバッグを用意しましょう。紙袋などは避け、フォーマル用のサブバッグを選ぶとスマートです。
必要な持ち物が入らない場合に備え、フォーマル用のサブバッグを準備しておくと安心できます。
靴の選び方:素材・デザイン・ヒールの高さ
足元も、全体の印象を左右する重要なポイントです。
喪服に合わせる靴は、黒無地のシンプルなパンプスが基本です。
素材は、布製が最も望ましいですが、本革や合成皮革でも光沢のないマットな質感であれば問題ありません。
エナメル素材やスエード素材(避けるのが無難)、爬虫類系の型押しなどは避けましょう。
デザインは、つま先とかかとが隠れるプレーンなものを選びます。
| 項目 | 推奨されるもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|
| 色 | 黒 | 黒以外 |
| 素材 | 布製(基本)、マットな本革・合皮 | 光沢素材(エナメル等)、スエード、爬虫類系、メッシュ素材 |
| デザイン | プレーンなパンプス(ラウンドトゥ、スクエアトゥ)、つま先・かかとが隠れる | オープントゥ、サンダル、ミュール、ブーツ、ローファー、派手な装飾(リボン、金具等) |
| ヒールの高さ | 3cm~5cm程度の太めで安定感のあるヒール | 高すぎるヒール(ピンヒール等)、ウェッジソール、ヒールなし(完全なフラット) |

足腰に負担が少ない靴を選びたいのですが…

ヒールの高さは3cmから5cm程度で、ピンヒールのように細いものではなく、安定感のある太めのヒールを選ぶと歩きやすく、疲れにくいですよ。
つま先の形は、丸みのあるラウンドトゥや、少し角ばったスクエアトゥが一般的です。
ご自身の足に合い、長時間履いても疲れにくい、歩きやすい靴を選ぶことが大切です。
アクセサリーのマナー:パールネックレス・イヤリング/ピアス・指輪
弔事の場でのアクセサリーは、基本的に結婚指輪(または婚約指輪)以外は身につけないのがマナーです。
ただし、唯一許容されるのがパールのアクセサリーです。
パールは「涙の象徴」とされ、お悔やみの気持ちを表すものとして認められています。
白、グレー、または黒のパールを選びましょう。
ネックレスは一連(シングル)のものを選び、「不幸が重なる」ことを連想させる二連(ダブル)以上のものは厳禁です。
| 種類 | 許容されるもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|
| ネックレス | パール(白・グレー・黒)、ジェット、オニキスの一連 | 二連以上、パール以外の宝石、ゴールド素材、華美なデザイン |
| イヤリング/ピアス | ネックレスと揃いの一粒タイプ(パール等) | 揺れるデザイン、大ぶりなもの、フープタイプ、ゴールド素材 |
| 指輪 | 結婚指輪、婚約指輪 | 上記以外の指輪 |
| その他 | – | ブローチ、ブレスレット、派手な腕時計、ヘアアクセサリー |

パールのネックレスは必ずつけなければいけませんか?

いいえ、アクセサリーは必須ではありません。つけない方がより丁寧とされる場合もあります。もし着用する場合は、一連のパールネックレスと、揃いの一粒イヤリング(ピアス)程度に留めましょう。
ジェットやオニキスといった、黒い宝石も弔事用として用いられます。
いずれの場合も、デザインはシンプルで控えめなものを選び、光り輝くものは避けるようにしましょう。
ストッキングの色と厚さの基本ルール
喪服を着用する際には、黒無地のストッキングを履くのがマナーです。
肌がほんのり透ける程度の、20~30デニールのものが一般的とされています。
厚すぎるものはカジュアルな印象になるため、基本的には避けましょう。
柄物や網タイツ、ラメ入り、カラータイツなどは厳禁です。
| 項目 | 推奨されるもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|
| 色 | 黒 | 黒以外、肌色 |
| 厚さ | 20~30デニール(肌が少し透ける程度) | 60デニールを超える厚手のタイツ(※)、素足 |
| 柄 | 無地 | 柄物、網タイツ、ラメ入り、ワンポイント |

寒い時期や、足が冷えるのが心配な場合はどうすれば良いですか?

真冬や寒冷地、またはご自身の体調によっては、防寒のために60デニール程度の少し厚手の黒無地タイツを着用することも許容される場合があります。無理せず体調を優先しましょう。
素足で参列することはマナー違反となりますので、季節を問わず必ずストッキングを着用します。
予備を一足バッグに入れておくと、伝線してしまった場合にも安心です。
ハンカチ・袱紗(ふくさ)・数珠(じゅず)の準備
喪服の装いでは、ハンカチ、袱紗、数珠といった持ち物も、マナーに沿ったものを用意することが大切です。
ハンカチは白または黒の無地が基本です。
袱紗は香典を包むために必須のマナーアイテムであり、紫や紺、グレーなどの弔事用の色を選びます。
数珠は仏式の葬儀に参列する場合に持参します。
| アイテム | 推奨されるもの | 避けるべきもの | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハンカチ | 白または黒の無地、綿・麻・ポリエステル | 色柄物、タオル地、華美な刺繍・レース | 控えめな同色の刺繍やレースは可の場合も |
| 袱紗 | 紫(慶弔両用)、紺・深緑・グレーなどの寒色系、無地 | 暖色系(赤・ピンク等)、派手な柄 | 香典を持参する際は必須。金封を裸で持ち歩かない |
| 数珠 | 自身の宗派のもの、または各宗派共通の略式数珠(一連) | – | 仏式の場合に持参。キリスト教式などでは不要。貸し借りはしない |

袱紗はどんなものを選べば良いか迷います…

慶事にも弔事にも使える紫色の袱紗を一つ持っておくと便利です。包み方が簡単な、金封タイプの袱紗もありますよ。
これらの小物は、いざという時に慌てないよう、事前に準備しておきましょう。
特に袱紗と数珠は、忘れずに持参したいアイテムです。
冬場のコート選びと注意点
寒い季節の葬儀や法事に参列する場合、コートの選び方にも配慮が必要です。
黒、濃紺、ダークグレーなどの地味な色の無地のコートを選びましょう。
デザインは、チェスターコートやステンカラーコートのようなシンプルなものが適しています。
素材は、ウールやカシミヤなどが一般的ですが、毛皮(ファー、フェイクファー含む)や革製のコートは殺生を連想させるため厳禁です。
| 項目 | 推奨されるもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|
| 色 | 黒、濃紺、ダークグレーなど地味な色 | 明るい色、派手な色 |
| 素材 | ウール、カシミヤ、ポリエステルなど | 毛皮(リアル・フェイク)、革、光沢のある素材(サテン等)、ダウン、キルティング素材 |
| デザイン | シンプルなデザイン(チェスターコート、ステンカラーコート等) | フード付き、トレンチコート、ダッフルコート、派手な装飾、大きなボタン |

ダウンジャケットやキルティングコートは避けた方が良いのですね?

はい、ダウンジャケットやフード付きのコート、キルティング素材などはカジュアルな印象を与えるため、弔事の場にはふさわしくありません。
会場に入る前にコートを脱ぐのがマナーです。
クロークがあれば預け、ない場合は裏地を表にして畳んで腕にかけておきます。
髪型・メイク(片化粧)・ネイルの整え方
身だしなみ全体も、控えめで清潔感のある状態に整えることが大切です。
髪型は、お辞儀や焼香の際に邪魔にならないよう、シンプルにまとめます。
ロングヘアの場合は、耳より下の低い位置で一つに束ねるか、シニヨンなどにしましょう。
メイクは「片化粧(かたげしょう)」と呼ばれる、色味を抑えたナチュラルなメイクを心がけます。
ネイルは、できればオフするのが望ましいですが、難しい場合は肌に近い目立たない色を選びます。
| 項目 | 推奨されること | 避けるべきこと |
|---|---|---|
| 髪型 | 清潔感を第一にシンプルにまとめる(低い位置で束ねる、シニヨン等) | 華美なアレンジ、後れ毛が多いスタイル、高い位置でのまとめ髪、派手な髪飾り |
| メイク | 片化粧(ナチュラルメイク):薄付きファンデ、色味を抑えたアイシャドウ・チーク | 濃いメイク、ラメやパール感の強いもの、派手な色の口紅、カラーコンタクト、つけまつげ |
| ネイル | オフする、またはヌードベージュ等の目立たないマットな単色 | 派手な色、ネイルアート、ラメ、ストーン、長い爪 |

ノーメイクで参列するのは失礼にあたりますか?

はい、大人のマナーとして、完全にノーメイクで参列するのは、かえって失礼にあたる場合があります。最低限の身だしなみとして、控えめな片化粧を心がけましょう。
派手な香水も避けます。
細部にわたる配慮が、故人への敬意とご遺族への弔意を表します。
全体のバランスを見て、清潔感と控えめさを意識した身だしなみを整えましょう。
購入?レンタル?70代に最適な喪服の準備方法
- 喪服を購入するメリットとデメリット
- 喪服をレンタルするメリットとデメリット
- 70代ならではの判断ポイント(着用頻度・体型変化・保管)
- 手持ちの喪服の状態チェックの重要性
- 購入とレンタルの組み合わせという選択肢
70代になると、弔事の席に参列する機会も増え、喪服の準備について考える場面が出てきます。
新しく購入するべきか、それとも必要な時にレンタルするのが良いのか、迷われる方もいらっしゃるでしょう。
どちらの方法にも良い点と考えるべき点があり、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切になります。
この章では、喪服を購入する場合とレンタルする場合のそれぞれのメリット・デメリット、70代ならではの判断ポイント(着用頻度、体型変化、保管)、そしてお手持ちの喪服の状態を確認することの重要性や、購入とレンタルを組み合わせるという選択肢について、詳しく見ていきます。
それぞれの特徴を理解し、ご自身にとって最も負担が少なく、納得のいく準備方法を見つけるお手伝いができれば幸いです。
最終的には、ご自身のライフスタイルや考え方に合った方法を選ぶことが、心穏やかに弔事に向き合うための第一歩となるでしょう。
喪服を購入するメリットとデメリット
喪服をご自身で購入しておくことには、安心感がある一方で、いくつか考慮すべき点もあります。
いざという時に慌てない備えができるのが最大の利点です。
購入する主なメリットとしては、急な訃報にもすぐに対応できること、そしてご自身の体型や好みにぴったり合った、着心地の良い一着を選べる点が挙げられます。
一方で、デメリットとしては、購入時にある程度のまとまった費用がかかること、保管スペースが必要になること、そして定期的なクリーニングや状態のチェックといった維持管理の手間がかかる点が考えられます。
また、年月とともに体型が変わって合わなくなる可能性も考慮する必要があるでしょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| いつでもすぐに着用可能 | 初期費用がかかる |
| 自分の体型や好みに合うもの | 保管場所が必要 |
| 長期的に見て割安になる可能性 | 定期的なメンテナンス(クリーニング、状態確認)が必要 |
| 安心感がある | 体型変化やデザインの陳腐化リスク |

やっぱり自分のものを一着持っておくと安心かしら?

急な時にも対応でき、ぴったり合うものを選べるのが利点です
購入を検討される際は、今後どれくらいの頻度で着用する可能性があるか、保管場所やお手入れの手間をどう考えるかなどを考慮して判断することが大切です。
喪服をレンタルするメリットとデメリット
着用する機会がそれほど多くない場合や、保管場所に悩みたくない場合には、喪服のレンタルサービスを利用するのも有効な選択肢です。
手軽さが魅力ですが、こちらも利点と注意点があります。
レンタルする主なメリットは、一回あたりの費用を抑えられる可能性があること、保管場所やクリーニングといった手入れの手間が一切かからないこと、そしてその時の体型に合ったサイズを選べる点です。
最新のデザインや、購入するには躊躇するような価格帯のもの、あるいは正喪服など特定の場面でしか使わないものも利用しやすいでしょう。
一方、デメリットとしては、急な弔事の場合に手配が間に合わない可能性があること、希望のデザインやサイズが必ずしも利用できるとは限らないこと、そして自分に合わせて仕立てたものではないため着心地の面で妥協が必要になる場合があることが挙げられます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 費用を抑えられる(着用頻度が低い場合) | 急な場合に間に合わない可能性 |
| 保管場所・手入れが不要 | 希望のデザイン・サイズがない場合がある |
| その時の体型に合ったサイズを選べる | 着心地が完璧ではない場合がある |
| 最新デザインや特定の格式も利用可能 | 着用頻度が高いと割高になる可能性 |
| 一時的な利用(購入前のお試しなど)に便利 | 事前の予約や手続きが必要 |

たまにしか着ないなら、借りる方が楽で良いかもしれないわね

保管場所やお手入れが不要で、体型の変化にも対応しやすいのが魅力です
レンタルを利用する場合は、急な必要性に備えて、事前にいくつかのレンタルサービスを調べておくと安心です。
着用頻度や利便性を考えて、ご自身に合うかどうかを検討しましょう。
70代ならではの判断ポイント(着用頻度・体型変化・保管)
購入かレンタルかを決めるにあたっては、特に70代という年代ならではの視点で考えてみることが大切です。
今後のライフスタイルや身体の変化を考慮に入れると、よりご自身に合った選択が見えてきます。
具体的には、以下の3つのポイントを考慮すると良いでしょう。
一つ目は「着用頻度」です。
今後、お付き合いの中で弔事に参列する機会がどれくらいありそうか、見通しを立ててみましょう。
頻繁に機会があると考えられるなら購入、それほど多くないと感じるならレンタル、という考え方が基本になります。
二つ目は「体型の変化」です。
年齢とともに体型は変化しやすくなります。
購入した喪服が数年後に合わなくなる可能性も考慮に入れる必要があります。
その都度ぴったりのサイズを選べるレンタルは、この点で安心感があります。
三つ目は「保管と手入れ」です。
喪服はデリケートな衣類であり、適切な保管と定期的な手入れが欠かせません。
ご自宅の収納スペースや、お手入れにかかる手間や費用が負担にならないかどうかも、判断材料となります。
| 判断ポイント | 購入が向いている可能性 | レンタルが向いている可能性 |
|---|---|---|
| 着用頻度 | 今後、参列する機会が多いと予想される | 参列する機会はそれほど多くないと予想される |
| 体型変化 | 体型の変化が比較的少ない、またはサイズ直しを厭わない | 体型が変化しやすい、またはその都度合うサイズを選びたい |
| 保管・手入れ | 保管スペースがあり、手入れの手間や費用が苦にならない | 保管スペースが限られている、手入れの手間を省きたい |

これからどれくらい着る機会があるか、体型も変わるかもしれないし、しまう場所も…

ご自身の状況やライフプランに合わせて、無理のない方法を選びましょう
これらの点を総合的に考え、どちらの方法がご自身の生活スタイルや考え方に合っているか、じっくり検討することが後悔しない選択につながります。
手持ちの喪服の状態チェックの重要性
新しい喪服の購入やレンタルを考える前に、まずはお手持ちの喪服が現在も着用可能かどうかを確認することが非常に大切です。
しまい込んだままになっている喪服が、いざという時に着られない状態になっている可能性もあります。
具体的にチェックしたいのは、主に以下の3点です。
第一に「サイズ」が合っているか。
特にウエスト周りや肩幅、腕周りなどが窮屈になっていないか、実際に試着して確認しましょう。
立ったり座ったり、腕を上げ下げしたりといった動作も試してみると良いです。
第二に「色褪せや生地の傷み」がないか。
喪服で最も重要なのは深い黒色です。
日光や経年変化で色が薄くなっていたり、虫食いや擦り切れ、テカリなどがないか、明るい場所でよく確認してください。
第三に「デザイン」が古く感じないか。
喪服のデザインは流行に左右されにくいとはいえ、あまりにも時代遅れに感じるものは避けたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
| チェックポイント | 確認内容 |
|---|---|
| サイズ | 現在の体型に合っているか(ウエスト、肩幅、腕周りなど)、動きやすいか |
| 色褪せ・生地の傷み | 深い黒色が保たれているか、虫食い・擦れ・テカリなどがないか |
| デザイン | 年齢や現代の感覚から見て、著しく古く感じないか |

タンスにある喪服、まだ着られるかしら…確認しないと

まずは現状を把握することが、最適な選択への第一歩です
もしお手持ちの喪服に問題がないようでしたら、それを活用するのが最も経済的です。
もしサイズが合わない、色褪せている、デザインが気になるなどの点があれば、新しく購入するか、レンタルを利用するかを具体的に検討する段階に進みましょう。
購入とレンタルの組み合わせという選択肢
喪服の準備は、必ずしも購入かレンタルのどちらか一方を選ぶ必要はありません。
それぞれのメリットを活かして、購入とレンタルを上手に組み合わせるという柔軟な考え方もあります。
例えば、最も着用する機会が多いと考えられる準喪服のアンサンブル(ジャケットとワンピースのセット)は、着心地の良いものを一着購入しておく。
そして、着用機会が限られる正喪服や、夏用・冬用といった季節に特化した喪服、あるいは体型が大きく変わってしまった場合などは、その都度レンタルを利用する、といった方法です。
また、パンツスーツを試してみたいけれど購入には迷う、という場合に一度レンタルしてみるのも良いでしょう。
- 基本の一着(準喪服アンサンブルなど): 購入
- 着用機会の少ないもの(正喪服、季節限定品など): レンタル
- 体型が大きく変わった場合: レンタル
- 試してみたいデザイン(パンツスーツなど): レンタル

なるほど、両方使うという手もあるのね

ご自身の状況に合わせて、柔軟に考えるのも良い方法です
このように、購入とレンタルを組み合わせることで、費用の負担を抑えつつ、必要な場面で適切な装いを整えることが可能になります。
ご自身のライフスタイルや価値観に合わせて、最も合理的で安心できる方法を検討してみましょう。
70代向け喪服の探し方:店舗・オンライン・レンタルの特徴
- 百貨店フォーマルサロンでの相談
- フォーマルウェア専門店の活用(B-GALLERY、東京ソワール等)
- スーツ量販店での選択肢(洋服の青山、AOKI等)
- 量販店・通販の活用(ニッセン、楽天市場等)
- オンラインレンタルサービスの利用(Cariru、相羽レンタル等)
- オンライン購入・レンタルの際の注意点
喪服を準備する際、どこで探すかは非常に重要なポイントになります。
ご自身の状況や希望に合わせて最適な場所を選ぶことで、納得のいく一着を見つけやすくなるでしょう。
選択肢は、百貨店、専門店、量販店、通販、そしてレンタルと多岐にわたります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、比較検討することが大切です。
| 探し方 | メリット | デメリット | おすすめな方 |
|---|---|---|---|
| 百貨店フォーマルサロン | 高品質、専門スタッフ相談、試着可能 | 価格帯高め、品揃えは店舗による | 品質重視、専門家のアドバイスが欲しい方 |
| フォーマルウェア専門店 | 豊富な品揃え、専門性高い、サイズ・機能充実、オンラインも便利 | 実店舗少ない場合あり、価格帯様々 | 幅広い選択肢から選びたい方、特定のニーズがある方 |
| スーツ量販店 | アクセスしやすい、手頃な価格帯 | 専門性は低い、品揃え・品質は限定的 | 手軽に実物を見たい方、価格を抑えたい方 |
| 量販店・通販 | 価格帯広い、サイズ豊富、自宅で選べる(通販) | 品質確認が必要(通販)、試着できない場合あり | 価格重視の方、多くの商品を比較したい方 |
| オンラインレンタル | 低コスト(低頻度)、保管・手入れ不要、体型変化に対応、多様な試用可能 | 急な対応難しい場合あり、選択肢限定的、完璧なフィット感は難しい | 着用頻度が低い方、保管・手入れが負担な方 |
これらの情報を参考に、ご自身のライフスタイルや予算、喪服に求める条件に最も合った場所を選びましょう。
百貨店フォーマルサロンでの相談
百貨店のフォーマルサロンとは、礼服や関連小物を専門に扱う売り場のことを指します。
質の高いブランドの喪服を取り扱っていることが多く、落ち着いた環境でじっくりと選ぶことができます。
最大のメリットは、フォーマルウェアに関する専門知識を持った販売員に直接相談できる点です。
サイズ選びはもちろん、マナーに関する疑問や、70代の体型に合うデザイン、着心地の良い素材など、細かな要望に応じたアドバイスを受けられます。
実際に試着して、生地の質感や着心地を確かめられる安心感は、他の購入方法にはない大きな利点です。

実際に試着して、店員さんに相談できるのは安心ね。

専門家のアドバイスは、特に初めての方や不安がある方には心強いです。
価格帯は比較的高めになる傾向がありますが、品質やサービスを重視し、長く大切に着られる一着を確実に選びたいと考える方にとって、百貨店は有力な選択肢となります。
フォーマルウェア専門店の活用(B-GALLERY、東京ソワール等)
フォーマルウェア専門店は、喪服や礼服、関連アイテムを専門的に取り扱っている店舗やオンラインストアです。
百貨店と同様に専門性が高く、質の良い商品を扱っていることが多いです。
特徴は、圧倒的な品揃えの豊富さにあります。
デザインのバリエーションはもちろん、大きいサイズや小さいサイズ、小柄な方向け、背の高い方向けなど、幅広い体型に対応したサイズ展開が魅力です。
また、前開きファスナー付きや自宅で洗える素材など、機能性に特化した商品も充実しています。
実店舗を持つ老舗ブランド(例:東京ソワール)から、オンライン販売を中心に展開するショップ(例:B-GALLERY、nina’s、Carette)まで様々です。
オンライン専門店の中には、自宅で試着できるサービスを提供しているところもあり、店舗に足を運べない場合でも安心です。
| 専門店名 | 特徴 | 主な販売チャネル |
|---|---|---|
| B-GALLERY | オンライン中心、幅広い品揃え、サイズ展開豊富、試着サービスあり | オンライン、一部実店舗 |
| 東京ソワール | 高品質、百貨店などでも展開、幅広い年代に対応 | 百貨店、専門店、オンライン |
| nina’s(ニナーズ) | オンライン中心、大きいサイズ・小さいサイズに強み、お手頃価格帯も | オンライン |
| Carette(カレット) | オンライン中心、洗える素材や機能性重視の商品が多い | オンライン |
豊富な選択肢の中から、自分の好みや体型、必要な機能にぴったり合った一着を見つけたい方にとって、フォーマルウェア専門店は非常に有効な探し場所と言えるでしょう。
スーツ量販店での選択肢(洋服の青山、AOKI等)
スーツ量販店というと、主にビジネススーツを扱うイメージがありますが、多くの店舗でレディースフォーマル、つまり喪服も取り扱っています。
洋服の青山やAOKI、コナカといった全国展開のチェーン店が代表的です。
これらの店舗で喪服を探すメリットは、店舗数が多く、自宅や駅の近くなどアクセスしやすい場所で見つけやすいことと、比較的手頃な価格帯の商品が多いことが挙げられます。
急に喪服が必要になった場合でも、身近な店舗で実物を確認し、購入できるのは便利です。
ただし、フォーマルウェア専門店と比較すると、デザインのバリエーションやサイズの選択肢は限られる傾向にあります。
また、品質や素材感も価格相応の場合があるため、よく確認する必要があります。

近所にあるお店なら、すぐに見に行けて便利かもしれないわ。

はい、アクセスしやすい点は大きなメリットです。まずは実物を見たいという場合に適します。
品質やデザインに強いこだわりがなく、アクセスの良さや手頃な価格を重視したい場合には、スーツ量販店も検討する価値のある選択肢となります。
量販店・通販の活用(ニッセン、楽天市場等)
量販店(スーパーマーケットの衣料品フロアなど)や、カタログ・オンライン通販(ニッセンなど)、そして大手オンラインモール(楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなど)でも、多様な喪服が販売されています。
これらの最大の魅力は、価格帯の幅広さと、豊富な選択肢です。
非常にお手頃な価格のものから、ある程度の品質のものまで、予算に合わせて選ぶことができます。
特にオンライン通販やオンラインモールでは、数多くのブランドやショップの商品を自宅にいながら比較検討でき、サイズ展開も豊富です。
ただし、特にオンラインで購入する場合は、実物の素材感や色味、正確なサイズ感を把握しにくいというデメリットがあります。
商品説明やサイズ表示を注意深く確認し、購入者レビューを参考にすることが重要です。
返品・交換が可能かどうかも事前に必ず確認しましょう。
| 購入場所 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 量販店(実店舗) | 実物確認可能、比較的安価 | 品揃え限定的、専門性は低い |
| カタログ・通販 | 自宅でゆっくり選べる、サイズ展開豊富 | 素材感・フィット感の確認困難 |
| オンラインモール | 膨大な商品数、価格比較容易、レビュー参考になる | 品質見極め必要、返品・交換条件確認必須 |
価格を最優先したい方や、とにかく多くの選択肢の中から比較検討したいという方にとっては便利な方法ですが、品質やフィット感を確かめられないリスクも伴うため、慎重な判断が求められます。
オンラインレンタルサービスの利用(Cariru、相羽レンタル等)
近年、喪服のオンラインレンタルサービスが充実しており、70代の方にとっても便利な選択肢となっています。
Cariru(カリル)や相羽レンタルなどの専門サービスを利用すれば、ウェブサイト上でデザインやサイズを選び、指定した日時に自宅や指定場所に届けてもらうことが可能です。
レンタルの最大のメリットは、着用頻度が低い場合に費用を抑えられること、そして保管場所やクリーニングなどのメンテナンスの手間が一切かからないことです。
体型が変わってしまっても、その都度ぴったりのサイズを選べる点も魅力です。
また、購入するには少し勇気がいるデザイン(例えばパンツスーツ)を試してみたい場合や、正喪服など特定の格式の喪服が一時的に必要な場合にも適しています。
急な弔事に対応できるよう、即日発送サービスを提供している業者もあります。

一度しか着ないかもしれないし、保管場所も要らないのは魅力的ね。

はい、特に着用回数が限られる場合や、メンテナンスの手間を避けたい方には便利な選択肢です。
着用回数がそれほど多くないと予想される方、自宅での保管や手入れを負担に感じる方、様々なデザインやサイズを試したい方にとって、オンラインレンタルは非常に合理的で便利な方法と言えるでしょう。
オンライン購入・レンタルの際の注意点
オンラインでの喪服の購入やレンタルは、自宅にいながら豊富な選択肢から選べる手軽さが魅力ですが、実物を見ずに決めることには注意が必要です。
失敗を防ぐために、以下の点を確認しましょう。
最も重要なのはサイズ確認です。
各社が提示しているサイズ表(バスト、ウエスト、ヒップ、肩幅、着丈、袖丈など)と、ご自身の体の寸法を正確に測って照らし合わせます。
同じ「9号」「11号」といった表記でも、メーカーやデザインによって実際の大きさは異なります。
素材や色味についても、商品説明をよく読み、「漆黒」「濃染加工」といった表記や、光沢の有無を確認します。
前開きファスナーや洗濯可能といった機能性も、必要な場合は明記されているかチェックしましょう。
商品写真だけでなく、実際に購入またはレンタルした人のレビューも参考になります。
万が一、サイズが合わなかったり、イメージと異なったりした場合に備え、返品・交換・キャンセルに関する条件は必ず事前に確認しておくことが不可欠です。
試着サービスがあれば、積極的に利用することをおすすめします。
- サイズ: 必ず自身の寸法を測り、各社のサイズ表と照合
- 素材・色: 説明文を熟読し、光沢の有無や漆黒の色味を確認
- 機能: 前開き、洗濯可否などの必要な機能を確認
- 写真: 様々な角度からの写真や着用イメージを確認
- レビュー: 他の購入者・利用者の意見を参考に
- 返品・交換: 条件を必ず事前に確認
- 試着サービス: 利用可能なら活用
オンラインの利便性を最大限に活用しつつ、これらの注意点を守ることで、納得のいく喪服選びにつながります。
よくある質問(FAQ)
- Q10年以上前の古い喪服は、まだ着ても問題ないでしょうか?判断基準を教えてください。
- A
10年以上経過した喪服でも、状態が良ければ着用できます。
ただし、いくつか確認すべき点があります。
まず、現在の70代のご自身の体型にサイズが合っているか試着しましょう。
次に、生地の色が褪せていないか、特に肩や袖などが日に焼けていないか明るい場所で確認してください。
喪服は深い黒色が基本です。
加えて、デザインがあまりにも古く感じないかも考慮点となります。
これらの点をクリアしていれば問題ありません。
もし合わない点があれば、買い替えやレンタルを検討するのがおすすめです。
- Qお腹周りをカバーできる喪服の選び方のコツはありますか?
- A
お腹周りが気になる場合、体のラインを拾わないデザインを選ぶのがコツです。
例えば、ウエスト部分に切り替えがなく、裾に向かって緩やかに広がるAラインのワンピースは、お腹周りを自然にカバーしてくれます。
また、ジャケットとワンピースがセットになったアンサンブルなら、ジャケットがお腹周りを隠す効果があります。
ウエスト部分にタックやギャザーが入ったデザインや、少しゆったりしたシルエットのチュニック丈のブラウスとパンツの組み合わせなども、体型カバーに役立ちます。
試着をして、締め付け感がなく楽に着られるか確認することが大切です。
- Q70代がパンツスーツの喪服を着る際に、特に気をつけるべき点は何ですか?
- A
70代の方がパンツスーツの喪服をお召しになること自体は、マナーとして問題ありません。
動きやすさや保温性の点でメリットがあります。
ただし、注意点として、必ず「ブラックフォーマル」または「喪服」として販売されているパンツスーツを選んでください。
ビジネス用の黒いパンツスーツとは、色味や素材感が異なります。
また、デザインはシンプルで、装飾の少ないものを選びましょう。
パンツの丈は、くるぶしが隠れる程度の長さが適切です。
立場によってはスカートスタイルの方がよりふさわしい場合もあるため、心配な場合は周囲に相談するのも良いでしょう。
- Q70代が喪服をレンタルする一番のメリットは何ですか?
- A
70代の方が喪服をレンタルする最大のメリットは、保管場所やクリーニングといった維持管理の手間が一切かからない点です。
年齢と共に体型が変化した場合でも、その時の自分に合ったサイズの喪服を手軽に利用できます。
購入費用を抑えられることも利点ですが、特に保管や手入れの負担がない点は、シニア世代にとって大きな魅力と言えます。
- Qオールシーズン対応の喪服一着だけで、夏や冬も乗り切れますか?
- A
オールシーズン対応の喪服(多くはジャケットと半袖または七分袖ワンピースのアンサンブル)は、基本的には一年を通して着用可能です。
ただし、真夏や真冬には工夫が必要になります。
夏場はジャケットを脱いでワンピースだけで過ごせるか、会場の空調を確認しましょう。
素材によっては暑く感じることもあります。
冬場は、ワンピースの下に保温性の高い肌着を着たり、厚手の黒ストッキング(またはタイツ)を履いたりするなどの防寒対策を行います。
必要であれば、喪服の上に着る弔事用のコートも準備してください。
より快適さを求めるなら、夏用・冬用それぞれの素材の喪服を検討するのも良いでしょう。
- Q急な弔問で、喪服用の小物(バッグや靴)が揃わない場合はどうすればよいですか?
- A
急な弔問で、どうしても喪服用の正式な小物(黒い布製のバッグやパンプスなど)が用意できない場合、最低限のマナーとして、できるだけ地味で目立たないものを選ぶように心がけます。
バッグは、光沢がなく、装飾の少ない、手持ちの黒いシンプルなハンドバッグで代用します。
靴も同様に、光沢のない黒のプレーンなパンプスがあれば理想的ですが、なければ地味な色の金具などが目立たない靴を選びましょう。
最も大切なのは、故人を悼み、ご遺族を気遣う気持ちです。
服装の準備が万全でなくても、弔意を伝えることが優先されます。
可能であれば、後日改めて正式な装いで弔問することも考えられます。
まとめ
この記事では、70代の女性が心穏やかに、そして自信を持って喪服を選ぶための大切なポイントを解説しました。
最も重要なのは、故人を偲び、ご遺族への敬意を表すためのマナーと格式を守ることです。
- 立場や場面に応じた適切な喪服の格式(正喪服・準喪服・略喪服)の理解
- 年齢と体型に合う、品格と快適さを兼ね備えたデザイン(シルエット・丈・素材・機能性)の選択
- バッグ、靴、アクセサリーなど、服装に合わせた小物選びのマナー遵守
- 購入とレンタルのメリット・デメリットを考慮した、自分に最適な準備方法の検討
これらの点を踏まえて、マナーを守りながらもご自身が心地よく過ごせる、最適な一着を見つけるお手伝いができれば幸いです。
安心して弔事の席に臨めるよう、この記事を参考に準備を進めてください。