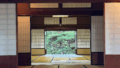障子の張り替えをDIYでやってみたいけれど、手順や道具の選び方が分からず不安になっていませんか。
例えば、次の悩みはありませんか。
- 初心者でもうまく貼れるやり方と、のりの扱い方が知りたい
- どの障子紙を選べばいいか、最新の選択肢も含めて迷っている
- 自分でやるメリット・デメリットを押さえ、プロ依頼と比較したい
本記事では、必要な道具のそろえ方と基本の7ステップ、失敗しないコツを一つに整理しました。
障子の張り替えDIYとは?自分でやる意義

障子の張り替えは、和室を清潔に保ちながら、費用を抑えて模様替えできる方法です。
DIYの基本をつかめば、のりの扱い方や貼り方のコツが分かり、日常のメンテナンスを自分で出来ます。
DIYのメリット(費用・時間・学び)
- 費用削減
材料費だけで済み、プロに頼むより安いです。
標準的な障子2枚なら、障子紙とのり、道具込みで数千円が目安です。
- 好きな時間に作業可能
休日や夜の空き時間で進められます。
和室の簡単な補修と同じ日に合わせても段取りがしやすいです。
- スキルが蓄積
頻繁ではありませんが、2〜5年ごとにやるほど上達します。
ふすまや壁紙の軽い補修にも応用できます。
手順通りに進めれば、初心者でも十分にきれいに仕上がります。
次は注意点を押さえて、失敗の芽を早めにつぶしましょう。
DIYのデメリット(仕上がり・枠補修・手間)
- 仕上がりにムラが出る
霧吹きの量やのりの濃さ、仮貼りのテンションで差が出ます。
のりムラやシワは初心者に起きやすい失敗です。
- 枠の補修が難しい
桟や枠が割れていると、補修にコツが要ります。
古い枠は無理せず状態確認が必要です。
- 手間がかかる
古紙剥がしとのりの除去、さらに乾燥時間が必要です。
梅雨や冬は乾きに時間がかかります。
これらは、道具選びとのりの管理、作業の順番を守るだけで大きく改善します。
具体的な対処は、後半の失敗対処でまとめています。
プロに頼む方が得なケース
- 枠や桟の破損が大きい、または歪みが強い
- 幅広桟や細格子、柄合わせが必要な柄入りの障子紙など高難度のデザイン
- 期限が短い、枚数が多いなど段取りの負荷が高い
こうしたケースは、結果的にプロの方が時間も仕上がりも安定します。
とはいえ、標準サイズの障子ならDIYで十分対応できます。
障子張替えに必要な道具と商品選び
下準備がそろっていると、作業は一気に楽になります。
のり貼り、両面テープ、アイロンタイプの違いも合わせて整理します。
必要な道具リスト(基本)
- 障子紙(無地/雲竜/強化・プラスチック障子紙・UVカットなど)
- 障子のり(デンプン系)、または両面テープ、アイロン貼り用
- 霧吹き(細かいミストが出るもの)
- カッター(刃はこまめに折る)、定規(アルミ尺)
- 刷毛またはローラー、のりバケツ、のり用ヘラ
- スポンジ、雑巾、バケツ(のり除去用)
- マスキングテープ(枠の養生)、新聞紙または養生シート
- 紙やすり、木工用ボンド(枠の軽補修)
- ドライヤー(乾燥補助)、ゴム手袋
道具は「足りない」をなくすことが仕上げの近道です。
刃とのりは多めに用意しておきましょう。
障子紙の選び方(強度・見映え・機能)
一般的な障子紙は扱いやすく、初めてでも貼りやすいです。
強化タイプやプラスチック障子紙は破れに強く、子どもやペットがいる家庭に向いています。
柄入りの障子紙は模様替えの効果が高い一方、位置決めやカットの精度が必要です。
近年は、のり付きタイプやUVカット、断熱性をうたう商品も増えています。
迷ったら「標準の無地」か「強化タイプ」が安心です。
光の透け方や白さは好みによるため、商品画像やレビューも参考にしましょう。
のり貼り/両面テープ/アイロンタイプの比較
| 方法 | 手間 | 仕上がりの自然さ | やり直し | 向いている方 |
| のり貼り | 中 | 高い | しやすい | 基本を学びたい初心者。コスパ重視 |
| 両面テープ | 低 | 中 | しにくい | 時短派。賃貸でのり汚れを避けたい |
| アイロン貼り | 低 | 中〜高 | ややしやすい | 冬場の作業。温度管理が得意な方 |
どうしても迷うなら、王道は「のり貼り」です。
のりの濃さと霧吹きの量を覚えれば、仕上がりが安定します。
通販・ショップでの賢い買い方
- 幅と高さを正確に測り、各辺30〜50mmの余尺を見込んで購入する
- 複数枚ならまとめ買いの方がお得なことが多い
- カッターの替刃は多めに、のりは気持ち多めに用意する
- ふすま紙や壁紙を扱うショップだと、同時購入で送料と到着がまとまりやすい
準備が整ったら、次は具体的な手順です。
7つのステップを順に進めましょう。
張替え基本手順(7ステップ)初心者向け解説
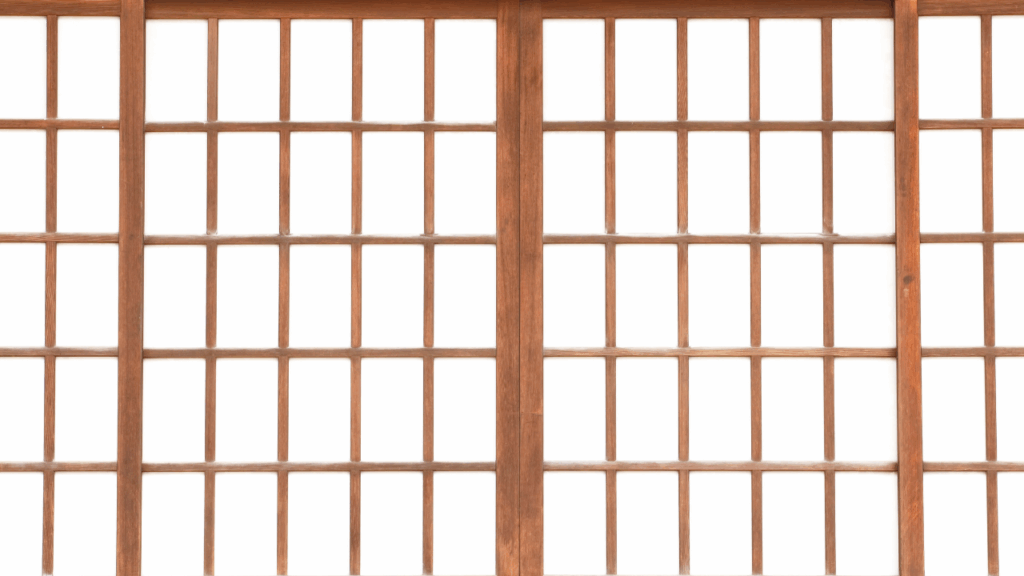
作業は「古紙剥がし→のり除去→のり付け→仮貼り→霧吹き→乾燥→カット」の順番です。
初心者は、仮貼りのテンションとのりの量、霧吹きの強さに注意しましょう。
古紙剥がし
桟に沿って霧吹きで軽く湿らせ、数分置いてから端からゆっくり剥がします。
のりが強い箇所は、ぬるま湯を含ませて再度湿らせると剥がれやすいです。
プラスチック桟は傷が付きやすいので、ヘラの角度に注意します。
焦らず、紙が切れないペースで進めましょう。
のり除去
桟と枠に残ったのりをぬるま湯でふやかし、スポンジやヘラで落とします。
のりが残ると新しい障子紙が浮く原因になります。
仕上げに乾いた布で水分を拭き取り、完全に乾かします。
ここが甘いと密着が悪くなるので丁寧に行いましょう。
のり付け
薄めた障子のりを刷毛やローラーで、桟に均一に塗ります。
濃すぎるとのりムラ、薄すぎると接着不良になるため、商品表示の希釈率を守ります。
角と枠はやや多めにのせると剥がれにくいです。
塗り忘れがないよう、一定の順路で回りましょう。
仮貼り
障子紙を上端からかぶせ、中央から外側に向かって空気を抜くように仮固定します。
無地は合わせやすいですが、柄入りは位置決めを丁寧に行います。
両面テープやアイロンタイプでも、仮置きの考え方は同じです。
引っ張りすぎず、たるませず、均一なテンションを意識します。
霧吹き
全体に薄く霧吹きをして、紙の繊維を軽く湿らせます。
乾くときにピンと張るため、かけ過ぎはシワの原因になります。
冬は部屋を少し暖めてから行うと乾燥が安定します。
ムラにならないよう距離を一定に保ちましょう。
乾燥
直射日光を避け、風通しの良い室内で自然乾燥させます。
ドライヤーを使う場合は30cm以上離し、弱風で均一に当てます。
梅雨や冬は時間がかかるため、夜貼って翌朝まで置くのが安全です。
急がずに待つことが仕上がりの鍵です。
カット
四辺の余りを定規を当ててカッターでカットします。
刃先はこまめに折り、引っかかりを防ぎます。
角は45度の「留め切り」にすると剥がれにくく、見た目もすっきりします。
最後に軽く霧吹きをして微調整しても大丈夫です。
ここまでが基本の流れです。
失敗しやすい点と対処法
初心者がつまずきやすいポイントを、原因と見直し、ちょっとした裏ワザの順でまとめます。
事前に知っておくと、作業中の迷いが小さくなります。
シワ・たるみ
原因は霧吹きのかけ過ぎ、のりの厚塗り、仮貼りのテンション不足です。
対処は霧吹きを「うっすら光る」程度にして、中央から外へ空気を抜くことです。
小さなたるみは乾燥後に軽く霧吹きで再調整できます。
紙の繊維方向を長辺に合わせるのも効果的です。
はがれ・のりムラ
角や端ののり切れが多く見られます。
角はのりを少し増やし、ヘラでよく圧着します。
のりムラは、綿棒で差しのりしてから軽く押さえてなじませます。
両面テープはローラーで圧着、アイロンタイプは中温と当て布で焦げを防ぎます。
桟や枠の割れ補修(木・プラスチック)
木部の小さな割れは木工用ボンドで固定し、乾燥後に紙やすりで平らにします。
欠けが大きい場合は埋め木や補修材を検討します。
プラスチック桟は専用接着剤や補修プレートが便利です。
構造的に弱いと感じたら無理せずプロに相談しましょう。
和室のふすまや壁紙へののり汚れ対策
作業前に養生シートとマスキングで周囲を保護します。
のりが付いたらすぐに水拭きして、最後に乾拭きします。
ふすま紙は水分に弱いので、雑巾はしっかり絞ります。
賃貸なら両面テープ式が安全です。
作業チェックリスト
チェックリストで抜け漏れを防ぎ、仕上がりの安定につなげましょう。
作業前後のチェックリスト
- 採寸は縦横+各辺30〜50mmの余尺を確保したか
- 道具一式を手の届く範囲に配置し、替刃は予備を用意したか
- 古紙剥がし後、のりは完全に除去・乾燥できたか
- のりの希釈は表示どおり、均一に塗れたか
- 仮貼りは中央→外側、柄の水平は取れたか
- 霧吹きは薄く均一で、たるみはないか
- 乾燥は直射日光を避け、十分な時間を確保したか
- カットは新しい刃で直線的に行い、角は留め切りにしたか
- 仕上がりを昼白色の明かりで最終確認したか
ここまで終えれば、和室の雰囲気が一新されます。
最後に、よくある疑問にも触れておきます。
よくある質問
何年ごとに張り替えるのが目安?
使い方にもよりますが、2〜5年ごとが一般的な目安です。
直射日光や結露が多い部屋は早めに劣化します。
強化タイプやプラスチック障子紙は耐久性が高く、周期を延ばせます。
毎年の大掃除で状態を見て判断しましょう。
ふすまと同日に作業しても大丈夫?
ふすまは重さやのり、道具が異なる場合があります。
同日にやるなら、粉の出る下地補修を先に済ませてから障子に移るのが安全です。
壁紙の補修も合わせるなら、最後に回すと汚れを最小限にできます。
段取りで仕上がりが変わるので、焦らず順番を守りましょう。
冬や梅雨の乾燥時間はどれくらい?
冬は室温を上げ、湿度40〜50%程度に整えてから作業します。
梅雨は除湿機や送風機を併用すると安定します。
乾燥時間は季節で2〜12時間ほど幅があります。
夜貼って翌朝まで置く進め方が失敗しにくいです。
【まとめ】
障子の張り替えを成功させるコツは、道具を整え、基本の7ステップを順番通りに進めることです。
仕上がり重視なら「のり貼り」が王道で、霧吹きは薄く均一、乾燥は焦らず、カットは新しい刃で直線的にが合言葉です。
強化タイプやプラスチック障子紙、のり付き商品など、用途に合う選択肢を選べば、模様替えの自由度が上がります。
仕上がりのムラや枠の補修の難しさも、準備とチェックリスト、動画での予習でしっかりカバーできます。
初めてでも大丈夫。
落ち着いて一つずつ進めれば、見違えるほどきれいに仕上がります。